『最後の鑑定人』第2話では、科捜研を去った土門の過去と、榊から投げかけられた「科学を裏切った」という衝撃的な言葉の真意が描かれ、物語は一気に深みを増しました。
かつて科学捜査の第一線で活躍していた土門が、なぜ今、独立した鑑定人として事件に関わっているのか──その背景が静かに浮かび上がります。
本記事では、“科学を裏切った”という言葉に込められた意味と、土門が科捜研を辞めた本当の理由について第2話のあらすじをもとに考察しながら、ネタバレを含めてわかりやすく解説します。
- 『最後の鑑定人』第2話のストーリー展開と事件の真相
- 土門が「科学を裏切った」と言われた背景とその意味
- 土門が科捜研を辞めた理由と彼の信念の核心
『最後の鑑定人』第2話のあらすじ
『最後の鑑定人』第2話は、科学では測れない“躊躇”や“家族愛”が複雑に絡み合う一件の銃撃事件を軸に展開されます。
承諾殺人を訴える妻と、それを取り巻く家族、さらには過去に科捜研を離れた土門の背景が徐々に明かされていく構成です。
ここでは、視聴者の理解を深めるために、事件の流れを整理して振り返ります。
依頼のない日常と土門への新たな依頼
未解決事件の鑑定を終えた土門と高倉柊子は、依頼が途絶えた日常に戻っていました。
そんな中、弁護士の相田直樹が訪れ、「承諾殺人の証明をしてほしい」と鑑定依頼を持ち込んできます。
依頼内容は、資産家・戸部庸三が自宅で銃殺され、その妻・佐枝子が「頼まれて撃った」と主張しているというものでした。
事件現場の状況と疑念の芽生え
現場は庸三の書斎で、2発の弾丸が発射された形跡が残っていました。
しかし、佐枝子の衣服や手からは射撃残渣が検出されており、「承諾殺人」としては矛盾の多い状況でした。
さらに、佐枝子は庸三の死亡直後に5分間、家を離れていたことが防犯カメラから判明し、疑いが深まっていきます。
榊との再会と“科学の対立”
土門は、現場に残された弾痕の不一致から、別の銃が使用された可能性に気づきます。
そして、証拠物鑑定のため訪れた先で再会したのが、科捜研時代の同僚・榊でした。
榊は、「薬莢の違いは報告済みだが、検察の指示がなかったため、それ以上の調査はしていない」と回答。
ここで彼は土門に向かって「お前は科学を裏切った」と告げ、二人の信念の違いが鮮明になります。
弾道解析とアバカ繊維の発見
土門は独自の鑑定を進める中で、アバカという植物繊維を庸三の書斎の床から検出します。
これは、庸三の娘・一美がフィリピンで運営するNPOで製品に使っていたものであり、彼女が現場にいた痕跡となります。
さらに、物置の窓枠にも射撃残渣が残されていたことで、発砲者は佐枝子だけでないことが明白となりました。
一美の犯行と佐枝子の“母性”
鑑定をもとに土門は公判前整理手続きの場で真実を提示。
一美こそが、庸三を殺害した真犯人だったのです。
一美はNPOの資金調達のために父に金を求めたが断られ、佐枝子を巻き込み犯行に及びました。
一方、佐枝子は「お母さん」と呼んでくれた一美を守りたかったと語り、家族への渇望から嘘をついていたことが明かされます。
事件の終息と“科学では測れないもの”
事件は科学鑑定によって解決されましたが、そこには人の心の弱さと切なさが交錯していました。
佐枝子が語る「冗談でも“お母さん”と呼ばれて嬉しかった」というセリフは、科学では計れない感情の重さを象徴しています。
そしてこの事件を通じ、土門自身が抱える過去と信念の葛藤もまた、浮き彫りになっていきます。
榊が土門に言った「科学を裏切った」の真意とは?
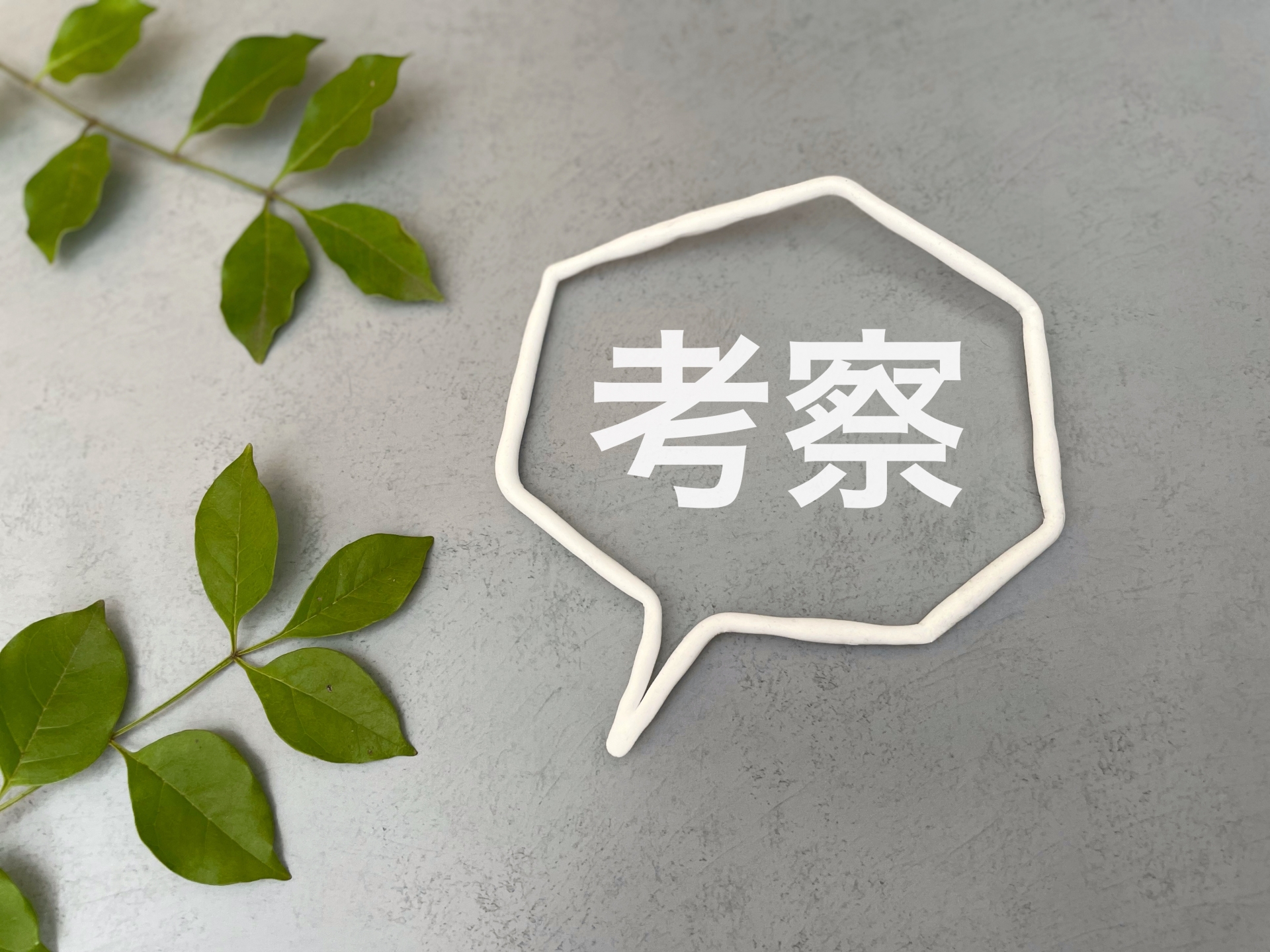
第2話で榊が土門に向けて発した「科学を裏切った」という言葉は、単なる皮肉ではなく、かつて同じ現場で働いた仲間だからこそ言える、重みのある非難だったと感じられます。
このセリフの背景には、過去に二人の間に何らかの確執、あるいは未解決のわだかまりが存在している可能性が高いと推測できます。
ここでは第2話の描写をもとに、榊のこの言葉の真意を多角的に考察してみます。
土門が“科学の手続きを踏まない”と見なされている可能性
榊は今回、土門の依頼に対しやや嫌々ながらも精緻な鑑定を提供しつつも、その過程で土門のやり方に違和感を抱いている様子でした。
榊の視点から見ると、土門のように検察や警察の正式な依頼を通さず、独自に鑑定を進める姿勢は、科学の枠組みを軽視しているように映ったのかもしれません。
つまり榊の「裏切り」という言葉は、科学的プロセスを飛び越えて自己判断で真実を導く土門のやり方そのものに対する違和感や反発だった可能性があります。
土門の“科学観”が変わったと感じている可能性
もう一つ考えられるのは、榊が知っている土門は「かつては組織内で科学を守る者」だったという過去の認識に基づく失望感です。
榊にとって土門は、かつて共に働いた信頼できる科学者だったはずです。
それが今では、検察の依頼も受けずに自らの信念で動く人物に変わってしまったように映り、裏切りと感じたのかもしれません。
つまり、榊の言葉には「あなたはもう、自分が知っていた科学者ではなくなってしまった」という失望の意味が込められていた可能性があります。
“科学そのものを歪めた”と感じた可能性
また、榊にとっての“科学”とは、依頼内容や証拠に忠実に、手続きを順守して鑑定を行う姿勢そのものかもしれません。
土門のように、「科学は嘘をつかない」という言葉を掲げながらも、実際には感情や正義感に動かされて行動することが、榊にとっては科学の純粋性を損ねる行為と映っている可能性も考えられます。
その場合、「科学を裏切った」とは、“科学を真理の道具ではなく、正義の道具にしてしまった”ことへの批判とも受け取れます。
以上のように、榊の言葉には単なる対立ではない、かつての信頼関係、科学への誇り、そして立場の違いによるすれ違いが重層的に込められていたと考えられます。
このセリフは、科学をどう信じるべきかという問いを視聴者にも突きつけてくる、非常に象徴的な場面だったのではないでしょうか。
土門が科捜研を辞めた本当の理由を考察
第2話では明言されなかったものの、土門が科捜研を辞めた背景には、組織の在り方や科学との向き合い方に対する強い葛藤があったと推察されます。
榊とのやり取りや、土門の一貫した言動からは、「科学は嘘をつかない。嘘をつくのは人間だ」という信念が今もなお彼の行動原理であることが伝わってきます。
ここでは、彼がなぜ科捜研という立場を捨て、独立した「最後の鑑定人」として生きることを選んだのか、その理由を掘り下げて考察していきます。
信じていた上司の不正と葛藤
科捜研の現場にいた土門が組織を離れるに至った大きな要因として考えられるのは、上司の不正を知ってしまった過去の事件です。
彼が語らずとも、榊との間にただならぬ空気が流れること、そして榊が過去をほのめかすような態度をとることから、土門が科学者として何か“決定的な選択”をしたことは間違いないでしょう。
仮にその不正が証拠の捏造や意図的な鑑定の省略であったならば、土門にとってそれは科学を汚す行為であり、見過ごすことができない一線だったはずです。
結果として、彼は上司に背くか、科学に背くかという選択を迫られ、科学の側に立つことを選んだのではないでしょうか。
科学を信じることで守りたかった“真実”
土門が繰り返し口にするのは、「科学は嘘をつかない」という信条です。
この言葉からは、彼がいかに科学を「真実に至るための手段」として信じているかがうかがえます。
組織に属していた頃の彼は、科学を使って社会に貢献するという使命感に燃えていたはずです。
しかし、組織の中で科学が都合よく扱われる現実を目の当たりにし、“守るべきは秩序ではなく、真実そのものだ”という覚悟をもったのでしょう。
その覚悟が、科捜研という組織から離れ、自らの手で鑑定を続ける「最後の鑑定人」としての道を選ばせたと考えられます。
つまり、土門にとって辞職とは逃避ではなく、真実を守るための「再出発」だったのです。
このように、土門が科捜研を辞めた理由には、科学者としての誠実さと、人間としての信念が深く関係していると考えられます。
そしてその過去は、今後のストーリーでさらに明かされていくことでしょう。
視聴者の感想と第2話の評価

『最後の鑑定人』第2話は、物語の展開だけでなく、登場人物のやり取りや演出面でも視聴者の注目を集め、多くのリアクションが寄せられました。
とくにSNSでは、キャラクター同士の“バディ感”や、“ある有名作品”を思わせるやり取りが話題となり、ファンの間で一種の盛り上がりを見せています。
ここでは、視聴者から寄せられた印象的な感想をいくつかの切り口でご紹介します。
「科捜研の女」とのリンクにファン歓喜
第2話で登場した“科捜研の榊”というキャラクターは、視聴者の多くに「科捜研の女」シリーズの榊マリコを連想させました。
“土門×榊”という構図が登場したことで、「これは完全にオマージュ!」、「シリーズ間のつながりを感じてニヤけた」というコメントが多く寄せられました。
ネット上では「土門が榊に会いに行くなんて、マリコはどこ?」といった妄想コメントまで見られ、メタ的な演出を楽しむ視聴者の声が多数見受けられました。
土門と柊子のバディ感に高評価の声
鑑定人・土門と研究員・高倉柊子のコンビネーションは、今回ますます魅力を増していました。
特に印象的だったのは、依頼を断ろうとする土門を、柊子が「営業的に必要です」と軽やかに押し戻す場面。
「土門の頑なさと、柊子の柔らかさの対比が絶妙」「バディとしてのバランスが良すぎる」といった称賛が集まりました。
この回では、人間味と論理が融合する2人の関係性に、多くの共感が寄せられたようです。
“ペンの持ち方”が魔法世界!?視聴者大爆笑
第2話でネット上が特に盛り上がったのは、土門と相田がペンを持つしぐさがまるで“魔法使い”のようだったという声です。
「ペンの持ち方が完全に杖でした😇ハリーとロン…ありがとうございます」
「元ハリーポッターとロンがペンを出して『先生、魔法は?』『使えるわけないでしょ』ってもうそれでしかないwwww」
こうした感想がX(旧Twitter)上でバズり、相田=ロン、土門=ハリー説まで飛び出す盛り上がりに。
このようなちょっとした仕草や演出の“絶妙な偶然”が、視聴者の遊び心をくすぐったようです。
以上のように、第2話はシリアスな展開の中にあっても、ファンが楽しめる“演出の隙間”が随所に散りばめられており、作品としての幅広さを見せつける回となりました。
『最後の鑑定人』第2話ネタバレ感想まとめ
『最後の鑑定人』第2話は、科学では測れない“感情”と“家族の絆”をテーマに据えた、非常に密度の濃い回となりました。
承諾殺人の真相をめぐる鑑定の過程はもちろん、佐枝子が“母親”として守ろうとした想いが視聴者の心に残るエピソードでした。
科学で立証できる事実と、人が人を想う気持ちとの間で揺れる物語構造が、深い余韻を残しました。
また、榊との再会によって描かれた土門の過去の断片と“科学を裏切った”というセリフは、彼の人物像をより重層的に見せるものでした。
あくまで事実に基づいて鑑定を行うという姿勢の奥にある、組織との摩擦や信念の代償が、今後さらに描かれることが期待されます。
柊子とのバディ関係の成熟もあり、作品としての広がりが出てきた点にも注目です。
さらにネット上では、“土門と榊”というネーミングの妙に「科捜研の女」ファンが反応するなど、メタ的な楽しみ方も多くの話題を呼びました。
ハリーポッター風のペンの持ち方という予想外の演出も相まって、視聴者の印象に強く残る一話となったことは間違いありません。
第3話以降も、科学と人間、真実と感情の間にある“グレーゾーン”をどう描くのか、その展開に注目が集まります。
- 第2話では承諾殺人をめぐる真相が明らかに
- 土門が「科学を裏切った」と言われた背景に注目
- 榊との再会が土門の過去を暗示
- 柊子とのバディ関係がより深まった展開
- 科捜研を辞めた理由は信念と対立による決断
- ハリポタ風演出や“榊”の登場に視聴者が反応





コメント