NHK土曜ドラマ『ひとりでしにたい』第5話では、鳴海が年下の同僚・那須田との関係に真剣に向き合い、その支配的な言動を「中二病」と喝破するシーンが話題を呼びました。
さらに、父・和夫が「家を売って介護マンションに入る」と宣言し、家族全体が終活の現実に直面するなど、コメディの中に現代的なテーマが凝縮された一話でした。
本記事では、第5話のあらすじを整理したうえで、介護マンションという選択肢の是非、終活を始めるタイミング、中二病と厨二病の違いを解説し、視聴者の感想や最終回への展望を考察します。
- ドラマ第5話の名場面と鳴海による“中二病”論破の詳細
- 介護付きマンションのメリット・デメリットと終活の始め方
- 「中二病」と「厨二病」の違いと現代的な意味の解説
『ひとりでしにたい』第5話のあらすじをシーンごとに整理
第5話は、鳴海が元カレや年下同僚との関係性の中で自らの価値観や生き方を見つめ直し、「終活」や「孤独死」といったテーマに向き合っていくターニングポイントとなる回でした。
とりわけ那須田との一騎打ちとも言える対話劇は、彼の“中二病”の本質を鳴海が見抜く名場面として視聴者の心を捉えました。
健太郎との再会:舐めていたのは自分だった
鳴海は元カレ・健太郎に、以前勧められて加入した保険の見直しを相談するため再び会いに行きます。
健太郎は終始、鳴海の話に耳を傾け、今回は「ペット保険」まで提案。
その丁寧な対応に、鳴海はかつて自分が彼を“ナメていた”ことを痛感します。
しかし彼は最後にこう言い放ちます。「彼氏いないの?俺は結婚してるけどな。スッキリした!」と。
一瞬ときめいた鳴海でしたが、その言葉にショックを受け、複雑な思いを抱えてその場を去ります。
那須田との確執:拒絶と誤解、そして沈黙
職場では那須田との関係が悪化。
鳴海は那須田を避けようとし、「話しかけてこないで」と突き放すような言葉をぶつけてしまいます。
それ以降、那須田は鳴海を無視するようになりますが、ある時ようやく話しかけてきます。
そして那須田は、自身の生い立ちに触れながら、「仲良くなりたい人とどう接していいか分からなかった」と告白。
親の模倣として支配的な態度をとってしまうこと、それでも鳴海とは信頼関係を築こうとしていたことを、真摯に語ります。
那須田の独白:不器用すぎる自己開示
彼は言います。「趣味を合わせようとした。まっとうに仲良くなりたかった。でも突然拒絶された」。
拒絶された不安と怒りが混ざり、再び親の真似をして“無視”という手段に戻ったことも吐露。
「相手を支配することで安心する」複雑な家庭環境の産物としての自己を説明し、「危機感が足りない山口さんに燃え移ってますよ」と警告して姿を消します。
母との通話:終活の現実を知る
動揺した鳴海は、母・雅子に電話をかけます。
母から、父・和夫が「家を売って介護マンションに入る」意向を持っていることを知らされ、鳴海の中で“終活”の問題がより現実味を帯びてきます。
母はこう助言します。「怖い相手は弱い相手にしか強く出られない」「ヒップホップの恰好ならナメられない」と。
それを聞いた鳴海は、逃げずに向き合う決意を固めます。
自宅での対峙:鳴海、論破の構え
休日、鳴海は那須田を自宅に呼び出します。
「これ以上関わりたくないけど、その前に借りは返したい」
「あの時君に一発かまされなければ、無意味な婚活を続けていたかもしれない」
「今度は私が君を論破する番だ!」と宣戦布告します。
“中二病”診断:支配と優しさの境界線
対話の中で、鳴海は「いつも正論で押しつぶしてくる那須田に、自分が悪いと思い込んでいた」と語ります。
そしてこう続けます。
「支配行動に気づかれないようにするのが巧妙だった」、「なんで自分からネタバレした?」
「くいころそうとしてるくせに、丁寧に説明して安堵させて解放する」
それはまさに、「メンヘラDVモラハラ野郎、つまり“ただのいい子”」
言い返す那須田に対して、鳴海は「早口になってんぞ!」と一喝。
そしてとどめのセリフ――「人心掌握術使うサイコ野郎。一般的になんていうか知ってる?…“中二病”だよ」
介護マンションのメリット・デメリットとは?
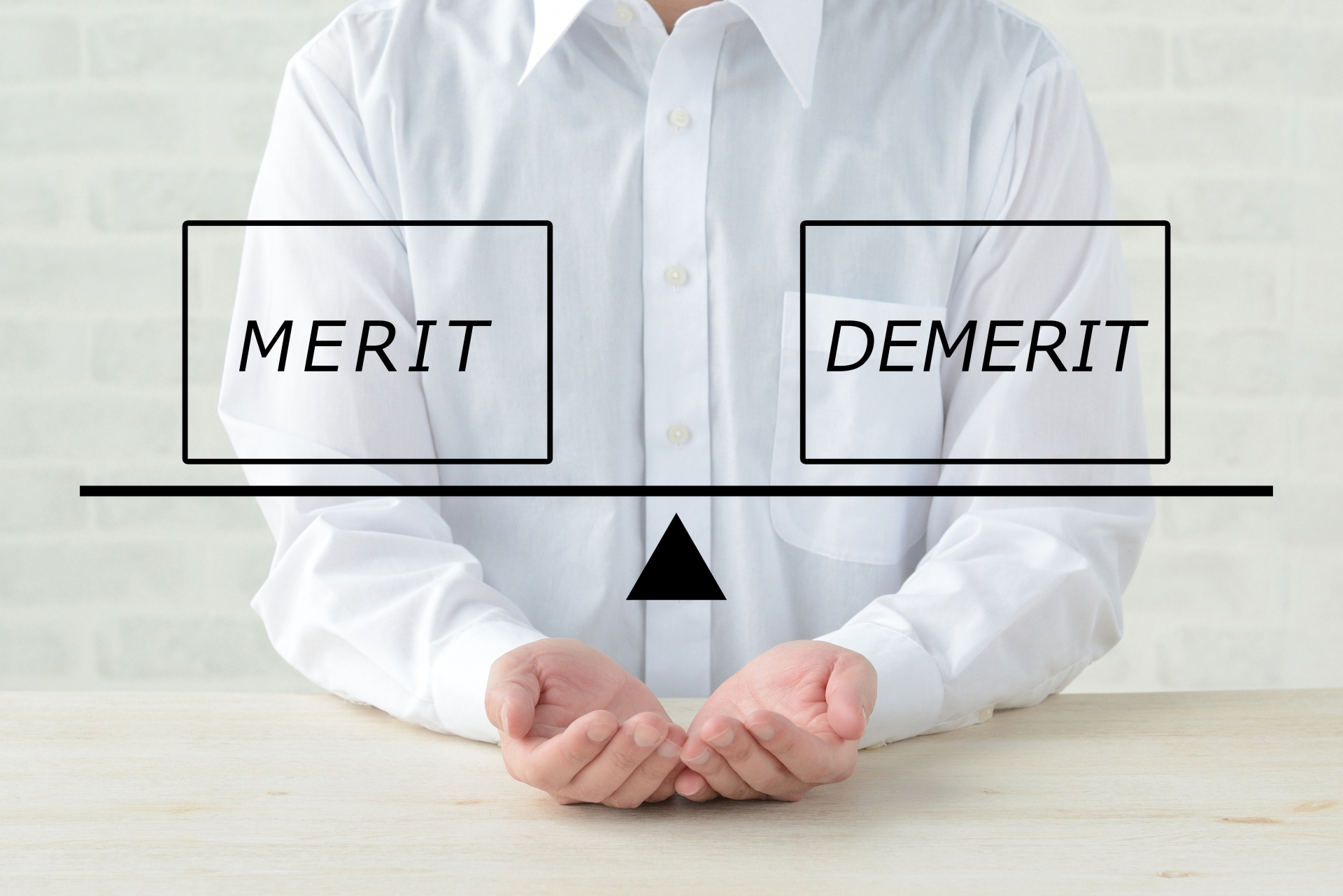
第5話では、鳴海の父・和夫が「家を売って介護付きマンションに入る」と家族に宣言します。
この発言は弟夫婦を驚かせると同時に、視聴者にも「介護マンションって実際どうなのか?」というリアルな疑問を投げかけました。
ここでは、介護マンションのメリットとデメリットを明確に整理し、終活の視点から考察します。
メリット:安心とサポートが得られる暮らし
介護付きマンションの最大の魅力は、生活支援と医療ケアの両立が可能な安心の住環境にあります。
スタッフが24時間常駐しており、緊急時には即時対応できる体制が整っています。
食事の提供や清掃、健康チェックなど、日々の生活全般を支援してくれるため、高齢者が無理なく自立した生活を送れるという点は大きな利点です。
また、同じ年代の入居者と交流できることで、孤立感の軽減や認知症予防にもつながるとされています。
こうした「老後の安心感」は、本人だけでなく、離れて暮らす家族にも大きな安心材料となります。
デメリット:費用・環境変化・家族との距離
一方、介護マンションの大きな壁となるのが経済的負担です。
多くの施設では入居一時金に数百万円~数千万円がかかり、加えて月額利用料も10万円前後が相場となっています。
そのため、和夫のように「家を売る」という決断が必要になるケースも少なくありません。
また、長年慣れ親しんだ自宅から離れることに対する心理的なストレスや、新たなコミュニティへの適応への不安も見逃せません。
さらに、施設に入ることで家族との物理的・精神的距離が広がる可能性がある点も懸念材料です。
介護マンションという選択は、「安心と自由な暮らし」を取るか、「慣れた環境と家族の近さ」を重視するか、人生の優先順位によって判断が分かれる問題です。
終活はいつから始める?きっかけとタイミング

第5話では、父・和夫が「家を売って介護マンションに入る」と告げた際、息子は「まだ早い」と戸惑いを見せました。
しかし和夫は、「終活は元気なうちに始めるものだ」と断言し、多くの視聴者にも示唆を与える場面となりました。
この章では、終活は実際にいつ頃から始めるのが理想なのか、一般的な傾向とともに解説します。
親の終活が自分の意識を変える契機に
家族が終活を始めたという話を聞いて、「うちはまだ早いのでは?」と反応する人は少なくありません。
しかし実際には、「何かあってから」では手遅れになりやすく、意思確認や資産整理、介護方針のすり合わせなどが困難になります。
元気なうちにこそ、家族と冷静に話し合いができる貴重なタイミングであり、それが終活における理想のスタート地点です。
遺言や相続、介護の希望などは、本人がしっかり意識を保っているうちでなければ意味を成しません。
60代以降が一般的だが、50代から始める人も増加
実際に終活を始める人の多くは60代後半から70代前半が多いと言われています。
しかし最近では、「親の介護をきっかけに自分も準備を始めたい」と考える50代の人も増えており、保険の見直しや持ち物の整理、エンディングノートの作成など、小さなステップから着手する人が増加中です。
とくに、介護施設の選定や財産管理の方針などは、早めに準備しておくことで、将来のトラブルや負担を軽減することができます。
「終活=死の準備」ではなく「生き方の選択」
終活というとネガティブな印象を持たれがちですが、実際は「より良く生きるための準備」としての意味合いが強くなっています。
今後の生活スタイルをどうしたいか、医療や介護にどう向き合うかを自分の意志で決めることは、人生の後半戦を前向きに設計する行為と言えます。
和夫のように、「自分の意思で選び、家族に負担をかけないようにする」という姿勢は、終活のあるべき姿の一つと言えるでしょう。
中二病とは?ドラマで描かれた“いい子”の裏側
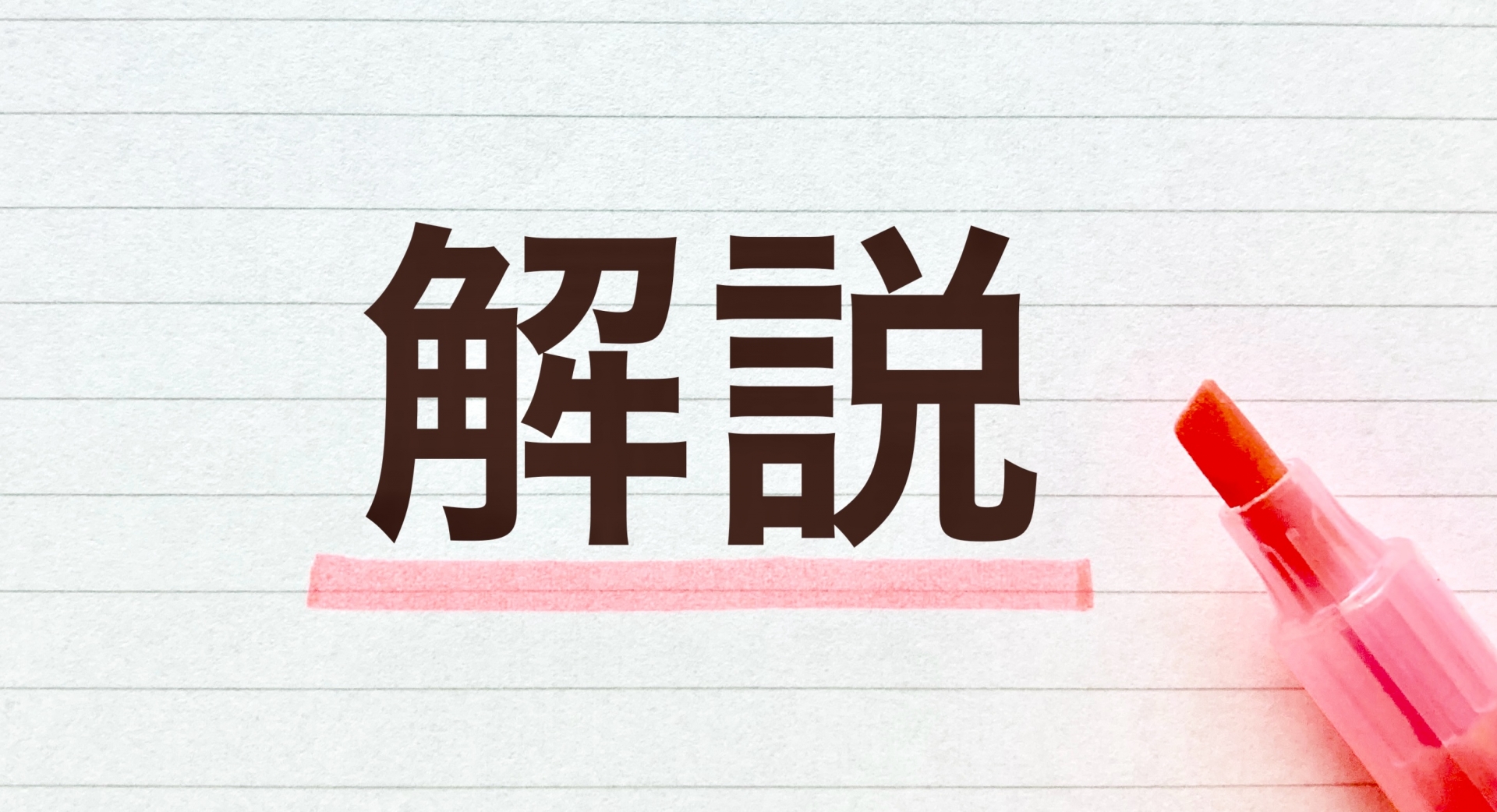
第5話のラストで、鳴海が那須田に投げかけた「それって中二病って言うんだよ」という言葉は、視聴者に強いインパクトを残しました。
このシーンは単なる皮肉ではなく、那須田の過剰な自意識や他者との関係性における歪みを突いた鋭い診断でした。
ここでは、中二病という言葉の正しい意味と、似た言葉「厨二病」との違いを解説します。
鳴海が那須田に言い放った“中二病”とは何か
「中二病」とはもともと、ラジオ番組で誕生した言葉で、中学2年生ごろの思春期特有の背伸びした言動や、過剰な自己主張を指します。
たとえば、「大人は汚い」「本当の親友が欲しい」といった思想にハマり、現実の自分より“大きくて特別な存在”に酔いしれる傾向です。
那須田の場合、「自分は人心掌握術を使うサイコ野郎」「危機感が足りない人に燃え移る」といった発言や、他人を無意識に支配しようとする行動が顕著でした。
それを鳴海は冷静に読み取り、「ただのいい子の癖に、中二病こじらせてるだけ」と喝破したのです。
厨二病との違い:ネットスラングと揶揄のニュアンス
「厨二病(ちゅうにびょう)」という言葉も広く使われていますが、これは「中坊(=中学生)」を意味するネットスラング「厨房」と「中二病」を組み合わせた表現です。
「中二病」が思春期にありがちな未熟な精神状態の“内面”を指すのに対し、「厨二病」は“痛々しい振る舞いや黒歴史”を笑いの対象として扱う傾向があります。
たとえば「自分にしか読めない文字を使う」「超能力を持っているふりをする」といった行動は、典型的な“厨二病ネタ”として知られています。
対してドラマで描かれたのは、単なる奇行ではなく、自己防衛のために他者を操作するという“人格構造そのものの未熟さ”でした。
鳴海が使った「中二病」という言葉は、笑いではなく人間関係における危うさを真正面から突く警告として機能していたのです。
この回は、「中二病」という言葉が単なる若者の癖ではなく、大人になっても抱える人間的な未熟さの象徴として深く掘り下げられた貴重な描写でした。
『ひとりでしにたい』第5話感想:中二病論破と終活テーマの融合が光る回

第5話は、「中二病」「終活」「家族の分断」など多様なテーマを見事に融合させた一話となりました。
視聴者からは、鳴海と那須田の対話劇や、父・和夫の決断をめぐる家族のやり取りに「自分の現実と重なった」という共感の声が多数上がっています。
笑いと痛みを織り交ぜながら、“ひとりでしにたい”という生き方に本気で向き合う人間たちの姿が印象的でした。
那須田の過去と鳴海の変化に共感の声
那須田が語った過去の家庭環境や、支配的なコミュニケーションにしか馴染めなかったという背景は、毒親やDVの経験者からの共感を呼びました。
一方、鳴海が「私はいつも悪いと思っていた」と語る場面には、“モラハラ被害者あるある”の構造が的確に描かれていたとの声も多く見られました。
それでも鳴海は「私が論破する番だ」と立ち上がり、自己否定から抜け出す過程を力強く示していました。
この変化は視聴者に「自分も変われるかもしれない」という希望を与えるシーンとなりました。
コメディと社会派テーマの絶妙なバランス
本作の魅力は、重いテーマを扱いながらもユーモアを決して失わない点にあります。
論破に挑む鳴海が、母の助言でヒップホップ風の服装+手書きタトゥーで身を固めるシーンは、痛快さと可笑しみが同居する名場面でした。
また、「中二病」「孤独死」「介護マンション」「結婚と家族」など、現代の未婚女性が直面しがちなテーマを真正面から描いた点も高く評価されています。
そのうえで、登場人物たちが少しずつ前を向く姿には、ドラマとしての爽快感とリアリティがありました。
第5話はまさに、「笑いながらも胸に刺さる」傑作エピソードと言えるでしょう。
まとめ:中二病、終活、そして最終回へ
第5話では、鳴海が那須田の“中二病”的な人格構造を見抜き、見事に論破するというインパクトのある心理戦が描かれました。
また、父・和夫が「家を売って介護マンションに入る」と宣言し、終活を“家族全体の問題”として突きつける重要な局面も訪れました。
本作らしいコメディと社会的テーマの絶妙なバランスが光った、まさに転換点となる回だったと言えるでしょう。
そしていよいよ、次回は最終回。
予告では、那須田が「あなたと一緒に居たら普通の子になれる気がした」と語り、改めて鳴海に告白する姿が描かれています。
長くこじらせてきた関係に、ようやく訪れる“本音の対話”がどう描かれるのか――視聴者の期待は高まるばかりです。
一方、山口家では和夫の終活発言に弟夫婦が真っ向から介入し、家族間の意見対立がさらにヒートアップ。
義妹・まゆの「ざまぁ、ですわね」という“爆弾発言”が誰に向けられたのかも注目ポイントです。
年下ハイスペック男子・那須田との関係を巡って、鳴海の立場にも新たな波乱が訪れる可能性があります。
「ひとりでしにたい」と言っていた鳴海が、誰かとのつながりや支えをどう受け入れていくのか。
最終回では、人生と死、独立と依存、そして“自分の居場所”についての答えが描かれることになるでしょう。
シリーズの集大成となる最終話――最後まで見届けたい内容です。
- 鳴海が年下同僚・那須田の“中二病”を論破する心理戦が展開
- 父の「介護マンション宣言」が家族に終活の現実を突きつける
- 介護施設のメリット・デメリットと終活の理想的な始め方を解説
- 「中二病」と「厨二病」の違いを丁寧に説明し、ドラマの意図を読み解く
- 共感と痛快さを両立した名場面が多く、視聴者の反響も大きい回
- 最終回へ向けた鳴海と那須田の関係、家族の対立にも注目が集まる







コメント