NHKドラマ10「舟を編む」第4話では、辞書作りに携わる人々の“こだわり”と“継承”が、さまざまな視点から描かれました。
図版や紙作り、日々の編集作業に宿るこだわり、そして過去から未来へと受け継がれていく情熱が丁寧に紡がれていきます。
なかでも、図版の“赤ちゃん天パ問題”に秘められていた父と子の物語は、伏線の回収とともに静かな感動をもたらしました。
- ドラマ第4話のあらすじを解説
- 赤ちゃん天パ問題に込められた伏線と父の想い
- 辞書作りに宿る“こだわり”とその継承の意味
「舟を編む」第4話あらすじを振り返り
第4話では、辞書『大渡海』の制作をめぐる多様な動きが展開されます。
紙作り、図版の見直し、そして父と子の関係に紐づく“天パ問題”など、シーンごとに具体的な出来事が連なっていきます。
それぞれの場面が丁寧に描かれることで、辞書作りに関わる人々の仕事と日常が浮かび上がっていきます。
蕎麦屋で語られる「申し子」誕生の背景
物語は、松本と荒木が蕎麦屋で過去を語る場面から始まります。
二人は荒木の定年退職が迫る中、後継者が見つからず焦っていた当時を振り返ります。
そこへ現れたのが営業部所属だった馬締光也で、西岡が彼を連れてきたと語られます。
馬締を見た松本は、辞書編集の適性をすぐに感じ取り、「辞書の申し子」と称します。
“申し子”という言葉には、「ある分野で特別な才能を持つ人」という意味と、「神仏に祈って授かった子」という語源があり、後者の意味も込められていると説明されます。
岸辺、紙作りの打ち合わせに向かう朝
紙作りを担当することになった岸辺みどりは、製紙会社「あけぼの製紙」の宮本との打ち合わせに向けて早起きします。
その際、早く家を出た岸辺を見て、馬締が「家中の時計が止まっていたのでは」と誤解し飛び起きる一幕もありました
玄関の姿見の話題から言葉の解釈へと会話が広がり、岸辺と馬締の関係性の変化も感じられるシーンでした。
あけぼの製紙での紙作り会議
あけぼの製紙では、宮本と岸辺が「究極の紙」を目指して打ち合わせを行います。
紙の厚み・強度・手触りなど細部にわたる仕様について話し合い、二人は共同で開発を進めていくことを決意します。
会議の終わりには、宮本が「接待させてください」と申し出て、岸辺を小料理屋「月の裏」へ誘います。
小料理屋「月の裏」での出会い
「月の裏」は馬締の妻・香具矢が営む店で、岸辺と宮本はここで食事を取ります。
宮本は香具矢が馬締の妻だと知って驚きつつも、その料理の写真をSNSに投稿します。
その投稿には「入口を作る会議」というタイトルが添えられており、岸辺も後日検索して嬉しそうに見つけ出します。
文学部バイト学生の登場と天童のこだわり
天童は、自身の後輩である文学部の学生たちを図版の語釈チェック要員として連れてきます。
学生たちは体育会系のノリで協力的に作業に入り、編集部の空気に変化を与えます。
また、天童が辞書を逆さに並べておくという独自の効率術を語る場面もあり、辞書との向き合い方に強いこだわりがあることが描かれました。
辞書編集部、図版会議を実施
編集部では10年間未着手だった図版の見直しが始まります。
河童が徳利を持っているか、丑の刻参りのろうそくの本数、アルパカやグリーンイグアナの姿など、イラストの細部まで検証されます。
岸辺も会議に参加し、柔軟な意見を出すことで議論を活性化させます。
図版担当イラストレーターの後継者を訪ねて
図版を手がけていた夏川実が既に亡くなっていたことが判明し、編集部は後継者を探すことになります。
馬締と岸辺は、実の息子・夏川颯太のもとを訪ね、図版の引き継ぎを依頼します。
颯太は父を「言われるがままに絵を描いていた人」と評し、軽んじていました。
赤ちゃんの天パ問題、伏線が明かされる
図版会議で取り上げられた「赤ちゃんのイラストが全員天パ」という疑問について、驚きの事実が明かされます。
それは、颯太が赤ちゃんの頃に天然パーマだったことから、父・実が密かに息子をモデルに描いていたというものでした。
岸辺が天パの赤ちゃんイラストを颯太に送信すると、颯太は深く感動します。
ここで、図版にもまた「思いが込められていた」ことが示されます。
西岡が馬締を連れてきた映画での経緯
映画『舟を編む』では、辞書編集部の後継者不足から始まり、馬締光也が配属されるまでの詳細な経緯が描かれています。
このストーリーは、辞書編集という仕事に求められる資質とは何かを浮き彫りにし、言葉に向き合う人間の姿勢が色濃く表されています。
特に、今回のドラマ第1話で岸辺みどりに出題された「右とは何か?」という問いが、映画では馬締への適性テストとして使われていた点も象徴的です。
荒木の定年と後任探しの始まり
物語は1995年、玄武書房に勤める辞書編集一筋38年の荒木公平が定年を迎えることから動き出します。
長年の盟友である辞書監修者・松本朋佑教授は、荒木の続投を希望しますが、荒木は病気の妻を介護するため、退職の意志を曲げません。
そこで、社内で急きょ後任探しが開始されますが、なかなかふさわしい人材が見つからず、編集部は難航します。
西岡が掴んだ「変人」馬締の情報
辞書編集部の若手・西岡正志は、当時同棲していた社内恋愛中の恋人・三好麗美から、ある情報を得ます。
それは、営業部に所属しながらも言語学専攻の院卒で“変人”と噂されている男・馬締光也についてでした。
馬締は真面目な性格である一方、コミュニケーションが苦手で社内では浮いた存在でしたが、言葉に対する深い理解を持っていると西岡は直感します。
荒木による「右の定義」テスト
西岡の紹介を受けた馬締は、辞書編集部を訪れます。
そこで荒木は、「右とは何か?」という抽象的かつ辞書的思考を問う質問を投げかけます。
この試験のような問いに対して、馬締は論理的かつ明晰な語釈を答え、荒木と松本を驚かせます。
この場面は、今回のドラマ版第1話で岸辺みどりにも同様の質問が投げかけられており、シリーズを通して辞書作りの本質を象徴する重要な問いであることがわかります。
馬締、辞書編集部へ異動
馬締の回答に心を打たれた松本教授は、新辞書『大渡海』の編纂にふさわしい人物として、彼を辞書編集部へ迎え入れます。
こうして、辞書の神に祈って現れたような存在として、馬締は“辞書の申し子”と呼ばれるようになりました。
この異動が、『舟を編む』という壮大な辞書制作の旅路の始まりとなります。
“申し子”として受け継がれる辞書への情熱
第4話では、「申し子」という言葉を通じて、辞書作りの精神や、それを支える人々の思いが語られました。
世代を越えて受け継がれていく言葉への情熱と、辞書に人生を賭ける人々の姿勢が印象的に描かれています。
岸辺みどりが“次の世代”として期待される中、馬締と荒木が担ってきた辞書編集の志が静かに伝わっていきます。
辞書編集部における“申し子”の意味とその重み
荒木と松本が蕎麦屋で語ったエピソードの中で、馬締のことを「辞書の申し子」と称する場面があります。
ここでの「申し子」には二重の意味があります。
一つは「ある分野において優れた能力を持つ者」という一般的な意味、もう一つは「神仏に祈って授かった子」という語源的な意味です。
荒木と松本は、馬締がまさにその両方に当てはまる人物であると語ります。
編集部の危機に際し、「どうか辞書編集にふさわしい人物を授けてください」と心の中で祈った結果として、馬締が現れた。
この流れは、辞書という存在が単なる編集作業の積み重ねではなく、思想と祈り、そして人の縁によって編まれていくものであることを象徴しています。
岸辺の可能性と馬締の信頼が未来を紡ぐ
物語の中では、馬締が岸辺のことを信頼している様子が随所に描かれています。
たとえば、図版会議での彼女の柔軟な発言や、製紙会社での粘り強い交渉姿勢に対して、馬締は静かに評価しています。
岸辺が編集部に加わったことで、馬締は自分がかつて受け継いだものを次の世代に渡す準備をしているようにも見えます。
荒木が馬締に託したように、今度は馬締が岸辺に辞書作りの精神を託そうとしている。
岸辺の成長は、辞書という文化が脈々と継承されていく過程の象徴として描かれています。
図版会議で浮かび上がる“こだわり”の本質
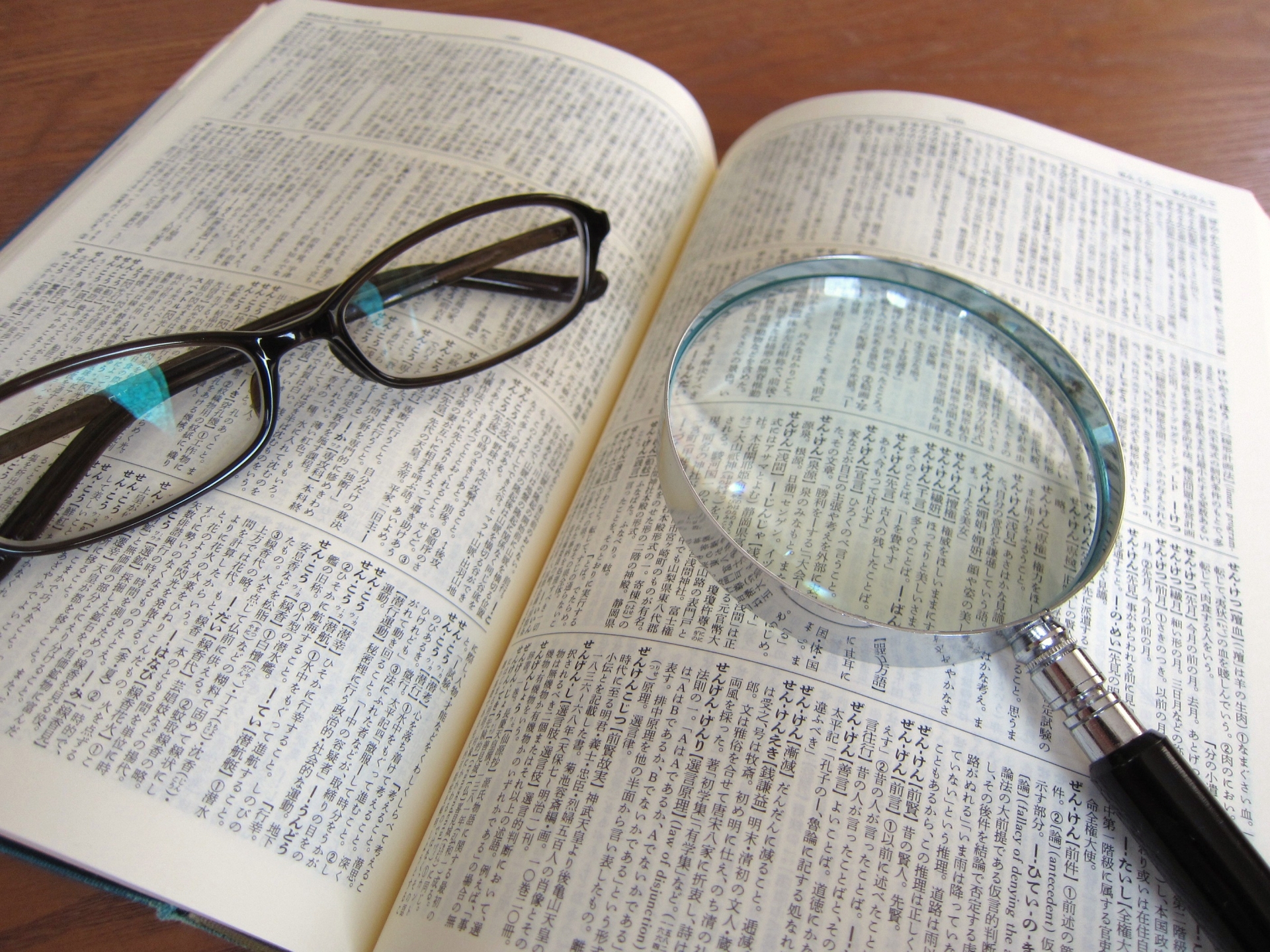
第4話では、辞書に掲載される図版(イラスト)の見直し会議が開かれ、図像表現におけるこだわりが明らかになっていきます。
「意味を正確に伝える」ことが求められる辞書において、イラストが果たす役割の大きさと、細部への徹底した配慮が描かれました。
視聴者にとってはコミカルに映る場面も多い中で、編集部の真剣な姿勢と“伝える技術”への意識が浮き彫りになります。
河童の徳利問題・イグアナの尻尾・丑の刻参りのろうそく本数など細部への熱意
図版会議では、長年手つかずだったイラストの見直しが本格的に開始されました。
会議に挙がったのは、河童が持つ徳利は適切か、グリーンイグアナの尻尾が長すぎるのでスペースをとる、丑の刻参りのイラストに描かれたろうそくの本数は正確かといった、一見些細とも思える内容です。
しかし辞書編集部では、こうした細部にも徹底してこだわることで、読者に対して信頼できる情報を提供する姿勢を貫いています。
会議には馬締、佐々木、天童、岸辺が参加し、それぞれが真剣な眼差しで図版を検証します。
特に岸辺の率直な意見が場を和ませつつも、新たな視点をもたらし、編集部のチームワークに新風を吹き込みました。
図版のイラストレーター・夏川実のこだわりの真実とは?
これらの図版を描いていたのは、かつて編集部と長く関わっていたイラストレーター・夏川実です。
実は既に故人であり、現在は息子の夏川颯太がその仕事を引き継いでいます。
颯太は「父はただ言われた通りに描いていた」と語り、「こだわりのない仕事だった」と感じていたようです。
しかし、辞書の図版という性質上、主観的な表現や過度な演出は避けられるべきであるため、むしろ「こだわらないこと」が必要とされていました。
馬締は颯太に、「お父様はこだわらないことにこだわっていたのではないか」と伝えます。
この言葉は、図版作成という裏方の仕事においても、深い美意識とプロフェッショナリズムが求められていたことを象徴しており、颯太の表情に変化を与えるきっかけとなりました。
“赤ちゃん天パ問題”で涙の伏線回収

第4話では、図版会議で話題に上がった「赤ちゃんのイラストが全員天パ(天然パーマ)」という不思議な共通点の背景に、
思いがけない伏線と家族の愛情が隠されていたことが明らかになります。
コミカルに始まったこの話題が、やがて静かな感動を呼ぶ展開へと繋がっていきます。
全ての赤ちゃんイラストが天パだった理由
図版会議で岸辺が気づいたのは、辞書に登場する複数の赤ちゃんのイラストがすべて天パで描かれているという点でした。
当初は「隠れキャラ的でいいのでは?」という軽い提案でそのまま通されていましたが、編集部では一応検討事項として取り上げられます。
やがて、それらのイラストを描いた故・夏川実の息子・颯太に事情を尋ねることで、その理由が明らかになっていきます。
颯太によれば、自分が赤ちゃんの頃天然パーマだったことを、実は父がこっそり図版に反映していたのだという事実が判明します。
つまり、赤ちゃんイラストの天パは、父・夏川実が息子への愛情を密かに込めたサインだったのです。
息子・颯太の胸に沁みる父親の想い
このエピソードを知った颯太は、当初「何のこだわりもなく描いていた」と見下していた父の仕事に、違った意味を見出すようになります。
馬締から「お父さんは、こだわらないことにこだわっていたのでは?」という言葉を投げかけられたことが、颯太の心を大きく動かします。
岸辺は、辞書に掲載された天パの赤ちゃんのイラスト画像をメールで送信し、颯太は静かにその画面を見つめます。
図版という“記号”にしか見えなかったイラストが、父から息子へ向けられた小さな愛のかたちだったことを知り、
颯太は初めて父の仕事の意味と向き合うことになります。
編集部で巻き起こった些細な疑問が、やがて一つの人生の物語として回収されるこの展開は、
視聴者に静かな涙を誘う印象的な伏線回収となりました。
辞書作りに込められた細やかなこだわりたち
第4話では、図版や紙作りに限らず、辞書編集に関わる日々の作業にも多くの「こだわり」が息づいていることが描かれました。
その中には、長年の経験から生まれた方法論や、編集者自身の信念が滲むような動作も含まれています。
一見地味な仕事の連続の中に、辞書作りという営みの奥深さと重みが表れていました。
「こだわり」という言葉の意味と使い方
もともと「こだわり」は「些細なことに必要以上に気を取られること」という否定的な意味を持つ言葉でしたが、
現代ではむしろ「自分なりの価値観や美意識を大切にすること」といった肯定的な意味で用いられることが一般的です。
辞書を編集するという作業は、この“言葉の揺れ”や“意味の変遷”に常に向き合う作業でもあります。
第4話に登場する様々なシーンは、まさにこの「こだわり」という言葉の意味と向き合うエピソードとも言えるでしょう。
天童の辞書並べの流儀
辞書編集部のベテラン・天童は、辞書を上下逆さに並べるという独特のスタイルを実践しています。
この方法により、机からわずか3ステップで辞書を開けるようにしており、日常的な作業の中で無駄を省き、瞬時に次の仕事へ移れるよう考え抜かれた手法です。
こうしたルーティンは、表面的には小さな工夫に見えても、辞書という巨大な情報を扱う現場では作業効率を大きく左右する重要な要素となります。
また、若手の岸辺にとっても、こうした先輩の姿は、辞書作りに込められた精神や所作の重みを学ぶ貴重な機会となっていました。
まとめ:舟を編む第4話で描かれた“こだわり”の継承と感動の余韻
第4話では、辞書作りに関わる人々の姿を通して、“こだわり”とは何か、そしてそれがどのように受け継がれていくのかが丁寧に描かれました。
図版の細かな検証から、紙作りにかける熱意、辞書の並べ方といった日常の動作にまで、それぞれの“こだわり”がにじんでいました。
中でも、「赤ちゃん天パ問題」という些細な発見が、父と子を結ぶ静かな愛情の物語へと展開していく流れは、視聴者の心に深い余韻を残しました。
辞書編集部にやって来た岸辺みどりの成長もまた、この「こだわりの継承」というテーマに重なります。
馬締がかつて“申し子”として迎えられたように、今度は岸辺が次の世代へとその意志をつなごうとしています。
編集部の空気の中で、岸辺が少しずつ言葉と向き合い、辞書づくりに没頭していく様子は、文化のバトンを受け取る姿そのものでした。
一見地味に見える辞書作りという作業が、人と人をつなぎ、記憶を残し、未来へと続いていく営みであることを再認識させてくれる──
そんな深くて温かいエピソードが詰まったのが、第4話でした。
- 辞書編集部の図版会議で細部へのこだわりが明らかに
- 天パの赤ちゃんイラストに込められた父の愛情を回収
- 紙作りや辞書の並べ方にも編集者の信念が表現
- “申し子”としての馬締の背景と岸辺への継承の兆し
- 些細な違和感が感動の物語へと変わる構成が魅力






コメント