『最後の鑑定人』最終回がついに放送され、多くの視聴者が感動とともに疑問や考察をSNSで交わしています。
この記事では、最終回のあらすじを振り返りながら、特に話題となった「毒はいつ中和されたのか?」や、印象的だった高倉の「先生の元を離れたくない」の真意について深掘りしていきます。
あわせて、気になるツッコミどころや全話を通して感じた作品の魅力やメッセージ性についてもまとめました。
ドラマを見逃した方も、見たけれどモヤモヤが残っている方も、ぜひ本記事で最終話の全貌とその裏側をじっくりとご確認ください。
- 「最後の鑑定人」最終回の詳しいあらすじと結末
- 毒の中和タイミングや高倉のセリフの真意
- 視聴者が感じたツッコミ所とその解釈
「最後の鑑定人」最終回あらすじ
最終話では、13年前の毒殺事件と現在の殺人事件が交錯し、科学と人間の倫理が問われる展開が繰り広げられます。
事件の背後には、かつて科学に絶望した男・氷室崇志の存在が浮かび上がり、土門、高倉、尾藤らがそれぞれの立場から真実に迫っていきます。
以下、物語の流れをシーンごとに整理してご紹介します。
下垣の死と氷室からの挑発
尾藤宏香(松雪泰子)の無実を証明するため、土門誠(藤木直人)は元科警研職員・下垣満行の自宅を調査。
しかし、下垣はすでに毒物で死亡しており、遺体の傍には「土門へ H」という謎のメモが。
直後、土門のもとに氷室崇志(堀部圭亮)から電話が入り、「科学は嘘をつかない…そんな幻想を君はまだ信じているのか?」という挑発的な言葉が告げられます。
この言葉から、土門は事件の狙いが尾藤ではなく自分自身であると悟ります。
科学とITに長けた犯人像
都丸勇人(中沢元紀)の調査により、下垣の死因は未知の毒物による中毒死と判明。
さらに、科警研のサーバーには不正アクセスの形跡があり、犯人は科学とITの両方に精通していることが明らかになります。
そこで土門は、大学時代の同期でITの専門家・原田俊吾(袴田吉彦)に協力を依頼。
土門は毒物の鑑定を、原田はアクセス解析を進めることで、事件の輪郭が徐々に浮かび上がります。
病室の接触と記憶のフラッシュバック
その頃、氷室は医師を装い、入院中の尾藤の病室を訪問。
「走馬灯のように思い出すかもしれませんよ」と語り、自身の過去を綴ったノートを渡します。
高倉柊子(白石麻衣)が見舞いに訪れると、氷室はすでに姿を消しており、白衣を脱ぎ捨てた跡だけが残されていました。
すれ違った相田直樹(迫田孝也)はその違和感を覚え、後の追跡につながっていきます。
取調室での対峙と科学の倫理
一方、土門と尾藤は、13年前の毒殺事件で使われた毒と今回の毒が完全に一致していることを突き止めます。
氷室が当時の指南役であり、科学者として企業倫理に絶望した過去があることが判明。
取調室では、氷室が「科学は人を救いも殺しもする禁断の果実」と語り、土門が「科学は嘘をつかない。嘘をつくのはいつだって人間だ」と反論する、重厚なやり取りが交わされます。
誘拐、追跡、そして倉庫へ
記憶を取り戻した尾藤は、氷室こそが犯人だと断言。
同時に、氷室が高倉を誘拐。注射を打ち、車で連れ去る姿を相田が目撃。
土門たちは高倉の安否を案じながら、氷室の電話に含まれていた環境音や塗装片を手がかりに、居場所を特定します。
こうして、警察とSITが向かった先は、神経ガスが仕掛けられた廃倉庫でした。
神経ガス装置と緊迫の救出劇
倉庫内で、高倉は南京錠のかかった扉に閉じ込められ、神経ガスの発火装置が作動寸前。
高倉に薬品の特徴を伝えてもらいながら土門は中和剤を探しますが、氷室との会話から高倉は「この中に中和剤はない」ことを見破る。
緊張が高まる中、土門は「硫酸を南京錠にかけろ!」と高倉に指示。
しかし鎖はなかなか溶けず、カウントダウンが迫るなかで、都丸がバールで鎖を破壊し、高倉は間一髪で救出されます。
氷室の自殺未遂と逮捕
追い詰められた氷室は、自らの顔に薬品を吹きかけ自殺を試みるも、死には至らず。
それは毒がすでに中和されていたからであり、土門は「科学を裏切った罪はきっちり償ってもらいます」と告げます。
氷室は、科学を信じる土門の信念によって敗北し、警察に逮捕されます。
鑑定所での再出発
事件解決後、土門は高倉に「君は優秀だから、ここを辞めてもいい」と優しく諭します。
しかし高倉は「私はこの仕事が好き。先生と尾藤さんの“中和”ができなくなると困ります」と笑顔で返答し、鑑定所に残る決意を固めます。
再結束の焼き肉シーン
ラストでは、尾藤の快気祝いとして、土門・高倉・相田・都丸が焼き肉を囲みます。
土門と尾藤の“痴話喧嘩”を中和する高倉の姿が微笑ましく描かれ、チームの絆と平穏な日常の回復が静かに締めくくられました。
いつ毒を中和した?
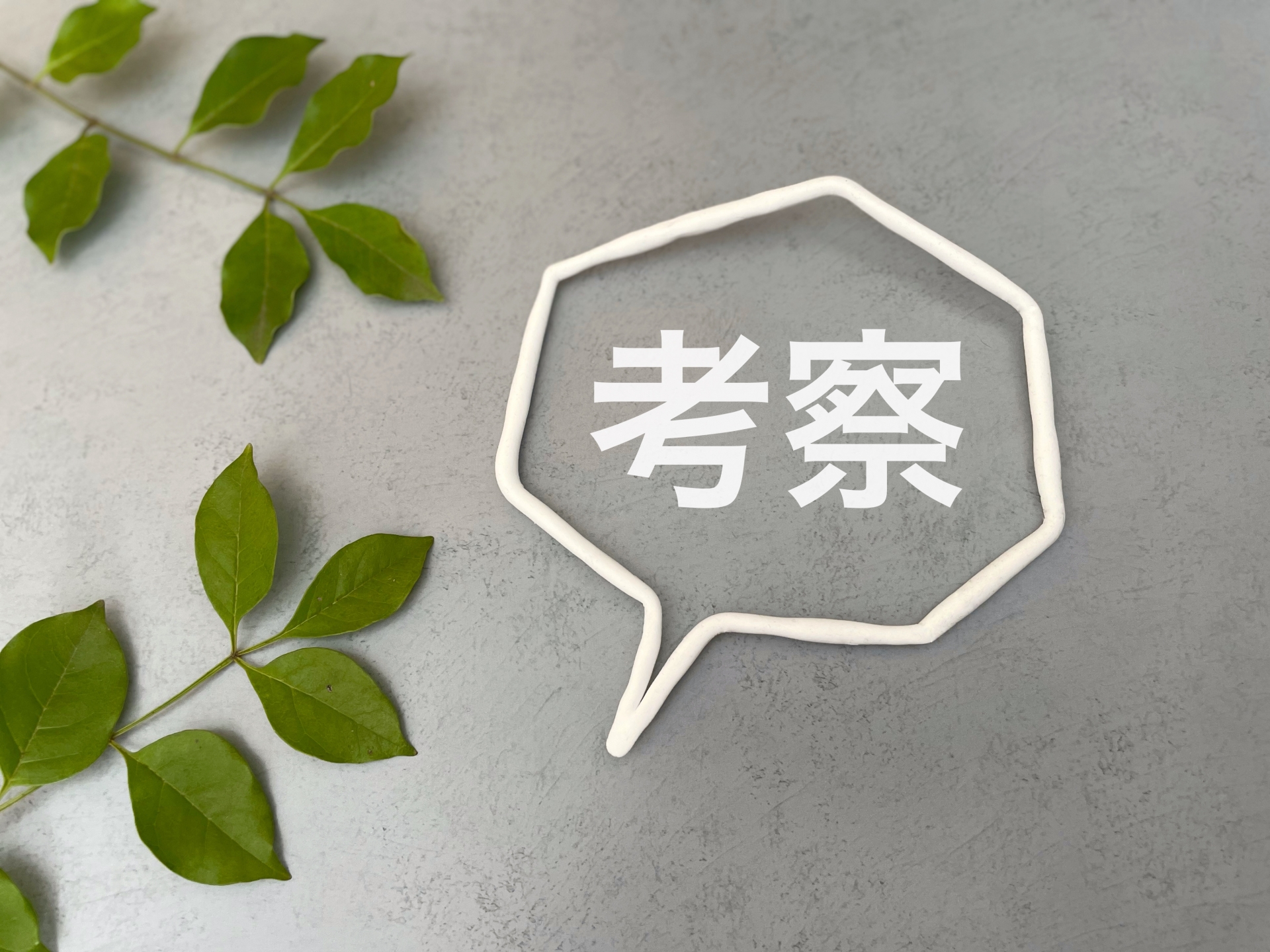
最終話で最も視聴者をざわつかせたのが、「毒はいつ中和されたのか?」という謎でした。
氷室はクライマックスで自らの顔に薬品を吹きかけ、自殺を試みますが、死に至ることはなく、その場にいた土門が静かに言い放ちます。
「毒は中和しました。科学を裏切った罪は、きっちり償ってもらいます」
その瞬間、多くの視聴者が「え?いつ?」と混乱
SNSでは放送中に、「氷室が吹きかけた薬品は毒だったはずでは?」、「中和剤はどこで使ったの?」といった疑問が多数投稿されました。
実は伏線が映像内に仕込まれていた
氷室が毒を吹きかける前、彼は薬品の小瓶を机の上に置いたまま、土門に背を向けて話し続けるシーンがあります。
会社員時代のこと、自分が科学を信じて裏切られた話を得意気に語っているその間、土門は背後で黙って彼の行動を見守っていました。
この描写が極めて重要です。実際にはこの間に、土門が薬品に準備していた中和剤をこっそり混入していたと考えるのが自然でしょう。
土門が中和した理由とは
なぜ土門はあえて毒を中和したのか? それには二つの可能性が考えられます。
- 氷室が自殺を図る可能性を見越していたため、命を守るために中和した
- 氷室が誰かに毒を吹きかけるリスクを排除するため、予防的措置として中和した
どちらにせよ、科学者として、人を殺させないための最後の理性が土門にはあったのです。
科学を信じる者としての矜持
氷室の計画は、自らの手で自分に毒を吹きかけることで“科学に殉じる”という演出でした。
しかし土門は、科学の力を人を救うために使うという信念のもとで、それを中和してみせました。
氷室が思い描いた「毒をもって科学を証明する」という復讐は、土門による“科学の中和”によって静かに終焉を迎えたのです。
ラストの「先生の元を離れてたくない」高倉の真意は?

最終話のラスト、高倉柊子(白石麻衣)が土門誠(藤木直人)に語りかけた「先生の元を離れたくありません」という一言は、視聴者の心に深く残るセリフとなりました。
そのあとに続く会話の“間(ま)”と、高倉の表情や言葉の選び方は、このセリフに複数の解釈の余地を持たせています。
この場面には、明確な言語では語られない“感情の揺らぎ”が込められていたように思います。
“間”が生んだ視聴者の想像力
高倉は「先生の元を離れたくありません」と言ったあと、「だって私は……」と言葉を途中で止め、間を置いてから「この仕事が好きなんです」と答えます。
この“間”が視聴者に与えたのは、「本当は別の言葉を言いかけたのでは?」という想像の余白です。
その後に土門が何かを察したような顔をすると、高倉はすぐに笑顔で「勘違いしないでください。先生のことは全然好きじゃないですから」と付け加えます。
恋愛感情なのか、信頼関係なのか?
この一連の流れをどう捉えるかは、まさに“視聴者の判断に委ねられた演出”でした。
高倉の表情、目線、間の取り方には、土門への好意とも取れる曖昧な気配がありました。
一方で、彼女自身が「この仕事が好きなんです」と断言したことから、科学を通じて人と向き合う仕事への誇りが原動力であることも間違いありません。
つまり、これは恋愛感情そのものというよりも、尊敬、信頼、仲間意識が混ざり合った“高倉なりの情熱”なのです。
「中和剤がいなくなっちゃいますよ」に込められたユーモアと覚悟
会話の締めくくりとして、高倉は「私が辞めたら中和剤がいなくなっちゃいますよ」と微笑みます。
このセリフには、土門と尾藤という“こじれた科学者たち”を繋ぐ存在としての自負が表れています。
つまり、高倉にとって土門のもとに残ることは、恋愛感情ではなく、自分の役割と使命を全うする決意の表明でもあるのです。
結論:恋心のようでいて、それを超える“居場所への愛着”
高倉の「離れたくない」は、恋心の一歩手前のような切なさと、科学者としてこの場所に立ち続けたいという意思の両方が混ざった言葉でした。
彼女にとって土門とは、尊敬する師であり、信じたい存在であり、自分を科学者として育ててくれる環境の象徴なのです。
だからこそ彼女はその場に残ることを選び、「私はこの仕事が好きなんです」とまっすぐな言葉で、その真意を伝えたのでしょう。
「最後の鑑定人」最終回のツッコミ所

「最後の鑑定人」は、科学と人間関係をテーマにした重厚なドラマでしたが、最終話には視聴者から思わずツッコミたくなるシーンがいくつか存在しました。
緊張感あふれる展開の中で、リアリティよりもドラマ性を優先した演出がいくつか見られ、「いや、それは無理があるのでは…?」と感じた方も多かったのではないでしょうか。
ここでは、ネット上でも話題となった代表的な「ツッコミ所」をピックアップして解説していきます。
なぜ警察が民間の鑑定所に捜査協力を?
まず一つ目のツッコミどころは、警察(県警)が事件の鑑定を民間の鑑定人に依頼しているという点です。
もちろん、土門は元科捜研所属のエキスパートであり、信頼と実績のある人物という設定ですが、現実の警察捜査では、まずは公的機関である科捜研が主体になるはずです。
視聴者の間では「なぜ土門が捜査の中心にいるの?」「民間に捜査の核心を任せすぎでは?」という疑問の声も上がっていました。
刑事は都丸ひとり? 捜査陣の少なさが気になる
誘拐事件発生後、現場で動いていた刑事はほぼ都丸勇人(中沢元紀)一人という描写。
事件の重大性や犯人の危険性を考えると、SITや他の刑事がもっと前面に出てもおかしくありません。
倉庫の突入シーンでも捜査陣の規模が小さく、「これは個人プレーすぎるのでは?」と違和感を覚えた視聴者も多かったようです。
南京錠を内側からかけて、誰がどうやって出た?
高倉が閉じ込められていた倉庫の部屋には南京錠が“内側から”かかっていたという設定。
これに対しては、SNSを中心に「え? じゃあ氷室はどこから出たの?」「内側から鍵をかけて、脱出方法がなかったら氷室も巻き込まれるでしょ?」といったツッコミが殺到しました。
物理的な仕掛けの説明がなされないまま進行したことで、サスペンスとしてのリアリティに疑問符がついた瞬間でした。
濃硫酸で南京錠を溶かす描写にリアリティが…
さらに注目されたのが、土門が高倉に「硫酸を南京錠にかけろ!」と指示する場面。
確かに濃硫酸は強力な薬品ではありますが、1分足らずで金属製の南京錠や鎖が溶けるのは非現実的という意見が多数。
また、「どうせ溶かすなら鎖の方が早いんじゃ?」という視聴者の冷静な指摘もあり、ここもドラマ的演出として割り切る必要がある箇所でした。
h3>まとめ:ツッコミ所も含めて“楽しめるドラマ”
これらの点は確かにリアリティを欠く部分ではありますが、ドラマ性やエンタメとしての緊張感を優先した結果とも言えるでしょう。
ツッコミながらも見入ってしまう…というのは、作品として魅力がある証拠です。
むしろ、こうした“ツッコミどころ”も含めて、視聴者同士で語り合える余地を残した点が、この作品の面白さでもありました。
「最後の鑑定人」最終回の感想

科学ドラマでありながら、人間ドラマとしても秀逸
最終話を見終えたとき、まず感じたのは「科学を扱うドラマとして、ここまで人間ドラマを深めたのはすごい」という驚きでした。
ただの推理劇ではなく、科学の倫理・矛盾・限界を真正面から描いた重厚なストーリーだったと思います。
氷室と土門の対比が深かった
特に印象的だったのが、氷室と土門の対比です。
かつて科学を信じていた氷室が、自らの正義のために科学を復讐の道具として使おうとする一方で、土門は「科学は人を救うために使うものだ」と一貫して主張します。
この“科学は嘘をつかない vs 科学は嘘を作るためにある”という対立構造が、このドラマの本質を深く語っていました。
高倉の成長が胸を打つ
高倉の成長もこの最終話の大きな見どころでした。
以前はミスを繰り返していた彼女が、今回は自分の意思で危機に立ち向かい、最終的には「この仕事が好き」と胸を張って言えるようになったことに、大きな変化を感じました。
その姿は、まさに“科学者としての覚悟”を身につけた瞬間だったと思います。
細かいリアリティは惜しいが、許容範囲
一方で、演出面や設定において「ちょっとベタだな」と思う場面も正直ありました。
濃硫酸で南京錠を1分で溶かす描写や、刑事が都丸だけで突入するなど、ややリアリティに欠けるシーンもあり、そこは賛否が分かれるかもしれません。
ただし、それらを差し引いても、全体としては非常に完成度の高い作品だったというのが率直な感想です。
レビューでも高評価が目立つ
ブログレビューでも「高倉らしさや都丸らしさがしっかり描かれていた」「科学で追い詰めていく演出が見事」といった評価が多く見られました。
また、「この雰囲気は水曜21時枠(他局)でやったほうがもっと受けたかも」という視点も興味深く、地味ながら質の高いドラマだったことは間違いありません。
セリフの“間”に感情が宿る丁寧な演出
終盤の会話に込められた“間”や含みも良く、視聴者に考える余白を残した演出がとても丁寧でした。
決して派手さで押すのではなく、人間の信念や選択、科学との向き合い方をじっくり描いたことが、このドラマの魅力だと改めて感じました。
「最後の鑑定人」まとめ
最終話では大きな事件が解決し、登場人物たちがそれぞれの役割や立ち位置を確かめ直すような穏やかな余韻が描かれました。
ですが、この物語の本当の価値は全11話を通じて積み上げてきた“科学と人間の関係性”の深い描写にあると思います。
“科学は中立”という信念と揺らぎ
このドラマが描いてきたのは、事件解決そのものよりも、科学を扱う者たちの心の在り方でした。
「科学は嘘をつかない」——その信念を軸にしながらも、現実では“科学を利用する人間”が常に関与し、揺らぎ、葛藤していることが丁寧に描かれてきました。
科学が万能ではないからこそ、それに携わる者の倫理・責任・信頼が問われ続けるという、静かで重たいテーマが全話にわたって一貫しています。
事件の裏にある“人間ドラマ”が魅力
毎話ごとの事件には、それぞれ背景に被害者・加害者の人生、悩み、選択がありました。
科学によって明らかになるのは証拠だけでなく、人の想い・嘘・守ろうとしたものなのだと、回を追うごとに実感できる構成でした。
だからこそ視聴者も、ただのミステリードラマとしてではなく、“人間を解剖するドラマ”として深く引き込まれていったのではないでしょうか。
キャラクターの成長と関係性の変化
土門誠という揺るがぬ信念の男を軸に、高倉柊子の成長、都丸刑事のひたむきさ、尾藤との複雑な関係など、キャラクター同士の距離感が少しずつ変化していく過程も見どころでした。
特に高倉の変化は顕著で、最終話では「中和剤」としての役割だけでなく、自分の足で立つ科学者として確かな存在感を見せてくれました。
続編への期待が自然と湧き上がる
全体を通して、登場人物の背景や人間関係にまだまだ掘り下げる余地があると感じさせる終わり方でした。
特に、土門・高倉・尾藤という個性的で相互補完的なトリオの関係は、今後もさまざまな事件と人間模様を描けるだけの深みがあります。
「科学を信じるということは、人を信じるということ」——そのメッセージをもっと多くのエピソードで掘り下げてほしいという想いから、続編やスペシャルドラマへの期待も高まります。
科学ドラマの新たな形を提示した傑作
『最後の鑑定人』は、サスペンスや法医学モノとは一線を画し、“科学の本質”を問いかけた稀有なドラマでした。
派手な演出や展開に頼るのではなく、静かに、しかし着実に「人と科学の物語」を紡いだ本作は、見応えと余韻に満ちた作品として、多くの視聴者の記憶に残ることでしょう。
終わってしまったことが寂しいと同時に、またこのチームに会える日が来ることを心から願いたくなる、そんなシリーズでした。
- 毒が中和された瞬間の伏線を丁寧に考察
- 高倉の「離れたくない」発言の真意に迫る
- 科学と倫理の対立を描いた最終話の見どころ
- リアリティに欠ける演出へのツッコミも紹介
- 高倉の成長と中和剤としての役割が印象的
- 事件の裏にある人間ドラマが胸を打つ構成
- 土門と氷室の科学観の違いが深いテーマに
- 続編を期待させる余韻あるラストシーン





コメント