2025年秋ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう(通称:もしがく)』第2話が放送されました。
本記事では、第2話のあらすじをシーンごとに振り返りながら、クライマックスで登場する「巨大な蚊取り線香」に込められた意味や、久部三成が演出する『夏の夜の夢』との関係性についても深掘りして考察していきます。
さらに、シェイクスピアの『夏の夜の夢』のあらすじ・第2話の感想や、次回・第3話のあらすじと見どころも網羅。
「なぜ『夏の夜の夢』?」「蚊取り線香の意味とは?」と気になっている方に向けて、ドラマの魅力と演出意図を丸ごと読み解く内容となっています。
- 『もしがく』第2話のあらすじと重要シーンの流れ
- 「夏の夜の夢」と久部の演出意図の関係性
- 巨大な蚊取り線香に込められた演出の意味や象徴性
「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」第2話のあらすじを解説
第2話では、WS劇場に迫る閉鎖の危機と、主人公・久部三成が新たな舞台「クベ版 夏の夜の夢」を立ち上げるまでの道のりが描かれます。
元演劇人とストリップ劇場の人々、そして法の介入──それぞれの立場や思いがぶつかり合いながら、ひとつの舞台が立ち上がる瞬間へと収束していきます。
ここでは物語の流れを、シーンごとに整理して紹介していきます。
劇場への摘発と「営業停止」処分
警察官・大瀬六郎がWS劇場に突入し、毛脛モネがパフォーマンス中に風営法違反で連行されます。
この摘発により、その夜は営業停止となり、劇場の存続が揺らぎ始めます。
久部とリカの再会、すれ違う価値観
ロビーをモップ掛けしていた久部三成に対し、トニー安藤は手伝いもせず、温度差が際立ちます。
一方、ホールでは倖田リカがクラシックバレエの振り付けを練習。美しい所作に見惚れた久部が「どうしてこんなところで働いているんですか?」と問うと、リカは強い語気で「こんなところって言った?」と反発。
この会話から、二人の過去や、価値観の違いがにじみ出ます。
神社での樹里との邂逅、ストリップへの嫌悪
久部は伴工作から、劇場常連のリボンさんの忘れ物を託され、神社を訪ねます。
対応した江頭樹里は、久部がWS劇場に勤めていると知ると「軽蔑します」と厳しく断じます。
久部が「ストリップは需要があるから成立している」と返し、樹里にリボンさんの劇場の忘れ物を渡す。
「常連さんみたいですよ」と聞いた樹里はめまいを覚えます。
「劇場が変わる」と語る蓬莱、久部を誘う
久部は蓬莱省吾に連れられ、彗星フォルモンや王子はるお、うる爺といった個性派たちのいるアパートへ。
「劇場がなくなるなら早く言ってほしい」という声が飛ぶ中、蓬莱は「WS劇場は大きく変わる」と語り、久部にも「手伝ってもらう」と告げます。
支配人が語るストリップの変遷と葛藤
WS劇場の裏手では、支配人・浅野大門が大瀬巡査に謝罪
大瀬は「僕はここの人たちが好きだから違法はしてほしくない」と本音を漏らす。
後に久部と話す中で、「ストリップも時代に合わせて変化してきた」という持論を語りつつ、今の経営状態への限界を感じていることを吐露します。
久部と過去の仲間たち──劇団解散の記憶
久部はトニーを連れてかつての小劇場「ジョンジョン」を訪れ、「夏の夜の夢」の舞台装置を回収します。
そこに現れた元劇団員・黒崎が「もう一度一緒に芝居をやりたい」と申し出ますが、久部はきっぱりと拒否。
ただし最後に、「旗揚げ公演を見に来てほしい」とだけ言い残し、劇場を後にします。
劇場閉鎖の宣告と、久部の逆提案
劇場ホールにダンサー・スタッフが集められ、大門支配人が「今月で閉館。今後はノーパンしゃぶしゃぶに」と発表。
驚く一同に餞別の封筒が配られますが、リカだけは拒否し、久部が「ちょっと待ってください!」と声を上げます。
渋谷の一等地にあるこの劇場を「東京一の小劇場に変える」と提案。久部は劇団運営の経験から年間2000人の動員や収支モデルを提示し、「利益は1500万円」と試算します。
反発するモネと、おばばの登場
リカと蓬莱は久部の提案に賛同しますが、モネは猛反対。「ストリップに誇りを持っている」と言い、久部の態度が気に食わないと感情をあらわに。
そこへ登場するのが伝説のストリッパー「おばば」。若手ダンサーに向かって「あんたらのやってるのは芸じゃない」と一喝し、フレと共にステージでタップダンスを披露。
その姿を見たリカは、「あんたに賭けてみる」と宣言。舞台への機運が高まります。
「クベ版 夏の夜の夢」始動──舞台中央に巨大な蚊取り線香
久部は演出助手に蓬莱を指名し、新たな脚本ではなくシェイクスピアの『夏の夜の夢』で勝負することを発表。
伴が幕を開けると、ステージ中央に立っていたのは巨大な蚊取り線香。
「クベ版 夏の夜の夢だ」と満面の笑みを浮かべる久部。第2話は、こうして新たな挑戦への希望を映しながら幕を閉じます。
シェイクスピアの『夏の夜の夢』とは?
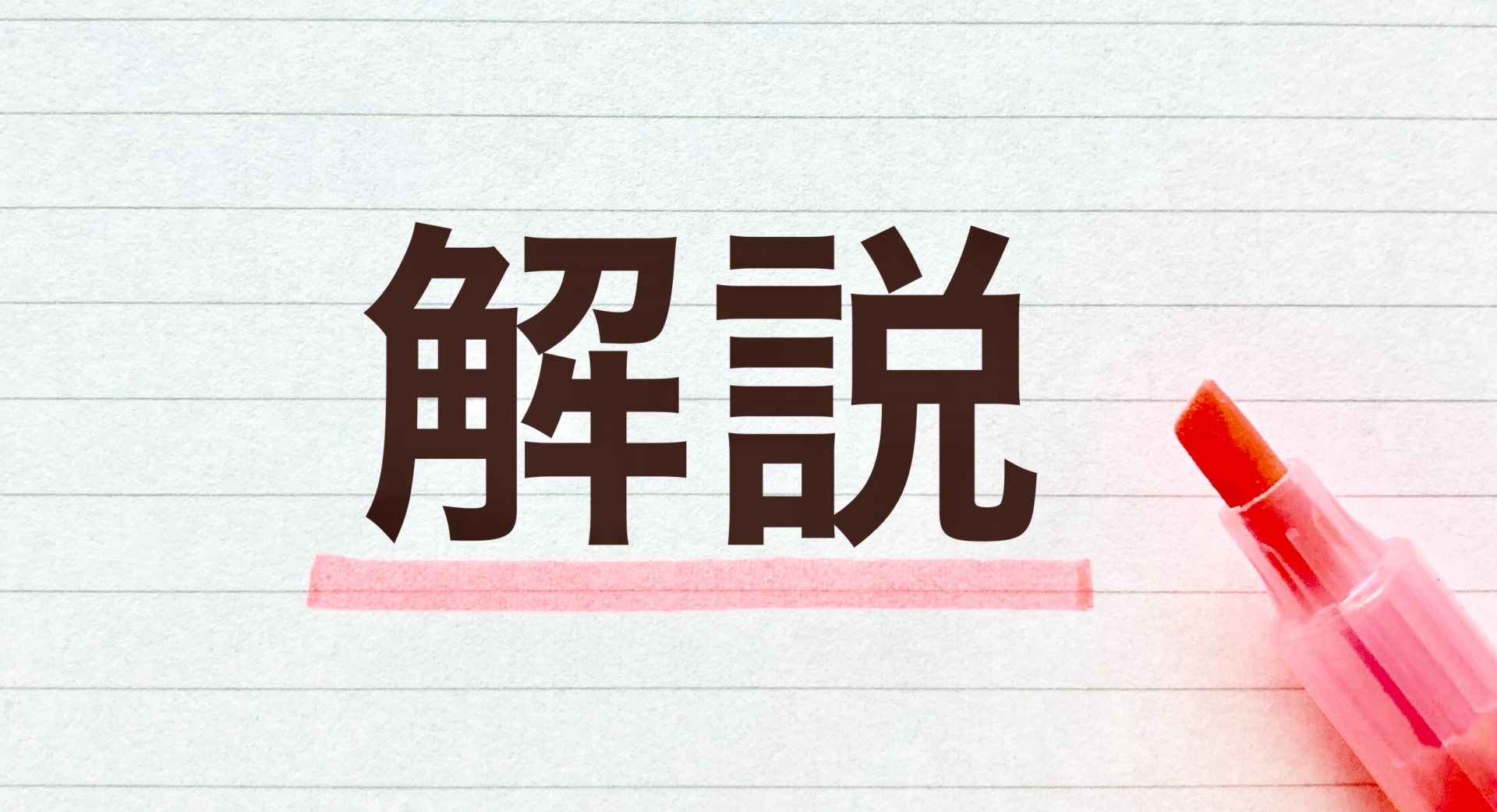
『夏の夜の夢』(A Midsummer Night’s Dream)は、ウィリアム・シェイクスピアが1595年頃に執筆した幻想喜劇で、恋と誤解、妖精のいたずら、夢と現実の境界が織り交ぜられた不朽の名作です。
物語の舞台は古代ギリシャ・アテネと、その郊外にある不思議な森。4人の若者の恋愛関係と、妖精たちの騒動、そして職人たちによる素朴な芝居の稽古が、夢のような一夜に交錯します。
『もしがく』で久部三成がこの作品を選んだのは、現実の制約から解放された場所=劇場という空間が、夢を語れる場所になるというテーマが、この作品に重なるからだと考えられます。
以下に『夏の夜の夢』のあらすじを簡単に紹介します。
恋と法律が交錯するアテネの宮廷
物語はアテネ公シーシアスとアマゾンの女王ヒポリタの結婚式を控えた宮廷で幕を開けます。
若者ハーミアは恋人ライサンダーと結ばれたいと願っていますが、父イジーアスは別の男・ディミートリアスとの結婚を強制。
イジーアスは古い法律に基づき、娘が従わないなら死刑にしてほしいと訴えます。公爵はハーミアに4日の猶予を与え、決断を迫ります。
恋人と芝居仲間たちが森に集う
ライサンダーとハーミアは駆け落ちを決意し、森で落ち合うことに。
このことを知ったヘレナ(ディミートリアスに片思い中)は、彼に告げ口をし、4人の若者全員が森へと向かうことになります。
一方で、公爵の結婚式の余興として芝居をすることになった職人たち6人も、夜の森で稽古をするため集まります。
こうして10人の人間たちが、妖精が住む幻想の森へ迷い込むのです。
妖精たちの魔法が招く恋の大混乱
森では、妖精王オーベロンと妖精女王ティターニアが「とりかえ子」を巡って口論中。
怒ったオーベロンは、いたずら好きの部下パックに命じて、媚薬の魔法をティターニアに仕掛けさせます。
媚薬は「目覚めて最初に見た相手を好きになる」効果があり、ティターニアはロバの頭に変えられた職人ボトムに惚れてしまうという珍騒動に。
さらにパックは、ライサンダーやディミートリアスにも媚薬を誤って使ってしまい、二人ともヘレナに恋するという逆転現象が起こります。
恋と現実の境界が崩れ、混沌とした「夢」の世界が広がっていきます。
魔法が解け、恋も芝居もハッピーエンドへ
オーベロンはティターニアを哀れみ、魔法を解いて和解。ボトムのロバ頭も元に戻されます。
ライサンダーとハーミアは元の関係に戻り、ディミートリアスはヘレナを本気で愛するようになり、2組の恋は成就。
イジーアスも死刑の訴えを取り下げ、若者たちはめでたく結ばれます。
最後は公爵とヒポリタの結婚式で、職人たちによる素朴で愛らしい芝居が披露され、すべての物語が円満に収束します。
こうして『夏の夜の夢』は、現実と幻想、秩序と混乱、恋と自己探求の物語として語り継がれていくのです。
「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」との関係性
『もしがく』第2話で久部三成が選んだ演目が、あえてシェイクスピアの『夏の夜の夢』だったのは、単なる有名古典というだけではなく、物語構造やテーマ性が作品全体と深くリンクしているからではないかと考えられます。
まず、『夏の夜の夢』の舞台となる“森”は、現実から一歩踏み出した「混沌と可能性の場」として描かれています。
これは、WS劇場を「ストリップ劇場」から「演劇空間」へと転換する構想が、まさに日常から解放された“異空間”を立ち上げようとする試みであることと重なって見えます。
また、登場人物たちの誤解やすれ違い、葛藤が“魔法”によって混乱を深め、最後に真実にたどり着くという構造は、劇場のダンサーや関係者たちが演劇を通して自分自身と向き合い、変わっていく過程を象徴しているようにも思えます。
さらに『夏の夜の夢』では、素朴な職人たちが公爵の前で劇を演じる“劇中劇”の構造がありますが、これは舞台経験のない人々が久部のもとで芝居を始めるWS劇場の姿に重なって見えるのではないでしょうか。
以上のことから、久部が『夏の夜の夢』を選んだ背景には、演劇を通して現実を一度「夢」に変え、そこから新たな現実を生み出そうとする意図があるのではないかと推察されます。
巨大な「蚊取り線香」の舞台装置に隠された意味を考察

『もしがく』第2話のクライマックスで登場した巨大な蚊取り線香は、ユニークな視覚的インパクトとともに、観る者に強い印象を残しました。
この舞台装置には、単なる装飾やネタ的演出にとどまらない、複数の象徴的な意味や意図が込められていると推察されます。
舞台設定を“日本風”にローカライズする演出
『夏の夜の夢』は本来、ギリシャを舞台にした物語ですが、現代演劇では舞台の時代や文化を“翻案”するのはよくある手法です。
今回の演出では、その物語を「1980年代の日本の夏」へと変換し、観客が一目で時代と季節を理解できるように巨大な蚊取り線香を象徴的に設置しているように思われます。
蚊取り線香=日本の夏というイメージは、縁側、夕涼み、花火大会といった郷愁的な風景とも結びつき、観客に“日本の夏の夜”を即座に伝える視覚的な装置として非常に効果的です。
妖精の世界と人間の世界の“ずらし”やユーモア
本来、人間が蚊を追い払うために使う蚊取り線香を、妖精の森という幻想的な世界にそのまま巨大化して持ち込むことで、現実と非現実の「ずれ」や「異化」が生まれます。
このサイズ感のギャップが、舞台上でのユーモアやナンセンスさにつながり、妖精という存在をどこか虫や小動物に近いものとして捉え直す視点にもつながります。
観客にとっては、「え、蚊取り線香?」「あれが森?」という意外性が笑いや親しみにつながり、ファンタジー世界への入り口となっているのです。
香りと煙による“夏の夜”の臨場感演出
蚊取り線香といえば煙と独特の香りが特徴的です。
実際の舞台で焚かれるかどうかは別として、このアイテムは嗅覚や視覚に訴える「五感の演出」としても非常に優れています。
渦を巻きながら立ちのぼる煙は、幻想的な空気を舞台全体に漂わせ、“夢”と“現実”の境界線を曖昧にする効果を持ちます。
『夏の夜の夢』が描く混沌とした恋愛模様や妖精たちの戯れは、まさにそうした“非現実的空間”の中で成立する物語であり、煙はその雰囲気を視覚的に体現しています。
「もしがく」との関係性
WS劇場の再起をかけて演劇に舵を切った久部が、選んだ題材が『夏の夜の夢』であること、そしてその舞台装置として蚊取り線香が登場することは、偶然ではないでしょう。
演劇への愛と、日本の夏という文脈を融合させて、ストリップ劇場から小劇場への転換を象徴的に表しているのかもしれません。
また、劇場を“脱ぐ場所”から“魅せる場所”へと変えていく物語の転換点として、この舞台装置は観客にも強くその意図を印象づける仕掛けとなっているように思えます。
まとめ
- 巨大な蚊取り線香は「日本の夏の夜」を象徴する視覚的サイン
- 現実と妖精の世界をデフォルメしたユーモラスな舞台演出
- 煙や香りを通じて五感に訴える“夢の世界”の臨場感演出
- 物語の転換点を示す象徴的な装置としての役割
こうした多層的な意味を読み取ることで、蚊取り線香という一見シュールなアイテムが、実は非常に巧妙な演出意図を秘めた舞台装置であるとに気づかされるかもしれません。
「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」第2話の感想

『もしがく』第2話は、物語の進行とともに登場人物たちの関係性が深まり、視聴者の心に残る展開となっていました。
まだ勢い不足な印象もあったものの、クライマックスでは久部の野心と熱量が一気に爆発し、物語の軸が明確に提示されたことが高く評価されています。
以下に、印象的だったポイントをいくつかご紹介します。
久部の“夢と野心”がようやく動き出す
展開がやや散漫で、登場人物たちが「渋谷にいるだけ」に見えていた初回とは違い、今回は久部が劇場を再生しようとする明確な目標を打ち出した点が好印象でした。
菅田将暉さん演じる久部の「目の奥に光る野心」や「一心不乱な目つき」が物語の牽引力となり、視聴者の期待を高める結果となりました。
演出・カメラワークと役者の表情がリンク
印象的だったのは、暗い舞台空間の中に立つ久部の表情。
その目が閃光のように輝き、「この男なら、面白いことをやってくれそうだ」という期待感を自然と抱かせてくれる演出でした。
視覚表現と役者の芝居が噛み合うことで、作品の熱量がようやく伝わってきた、という印象です。
巨大な蚊取り線香の“謎”が笑いと共に解明される
初回から謎だったポスターの「蚊取り線香」についても、ついにその正体が明らかに。
大きな蚊取り線香を背負う久部の姿に思わず笑ってしまうという声もありましたが、そのインパクトも含めて“舞台が始まる”というワクワク感を演出していたと感じられます。
「ここからが本番」と思わせる展開
次回から劇団を本格的に始動させようという展開になり、「あと3週間で劇場を立て直す」という一本の明確な軸が立ったことは、物語の期待値を大きく押し上げました。
「ようやく本当の『もしがく』が始まる!」という、そんな高揚感と期待が込められた第2話だったと感じられます。
「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」第3話のあらすじと見どころ

久部、ついに脚本執筆へ──「夏の夜の夢」日本版の創作開始
物語は、WS劇場の向かいにある古アパート・グローブ荘から始まります。
久部三成(菅田将暉)は、WS劇場で上演するためにシェイクスピア『夏の夜の夢』を現代風にアレンジした台本を執筆中。
しかし、その執筆は思うように進まず、理想と現実のギャップに葛藤する久部の姿が描かれます。
リカと蓬莱が久部に“現実”を突きつける
台本執筆に没頭する久部を見守るのは、蓬莱省吾(神木隆之介)。
夜食を届けに、同じアパートに住む倖田リカ(二階堂ふみ)の部屋を訪れます。
久部が完成させた原稿を読もうとするリカに対して、久部はなぜか異様なまでに防御的な態度を取ります。
リカと蓬莱が、「セリフは短く」「客が飽きる」などと言いたい放題に意見をぶつけると、久部はついに激昂して台本をビリビリに破り捨ててしまいます。
見どころ:夢と現実の狭間で揺れる久部の“創作の苦悩”
第3話では、ついに劇場再生計画の核心=台本作りが本格的に始動します。
しかしそれは、「自分の理想の演劇」と「WS劇場の現実」との間にあるギャップに向き合う作業でもあります。
久部のこだわりが、果たして観客や演者に受け入れられるのか。
創作とは誰のためにあるのかという問いが、回を追うごとに浮き彫りになっていきそうです。
リカと蓬莱の“鋭い現実感”との対比
久部の周囲にいるリカや蓬莱は、いずれも“夢”よりも“現実”を重視するバランサー的存在です。
この2人のキャラクターが久部にどう影響を与え、どのように演劇が形になっていくのか、そのプロセスが大きな見どころとなるでしょう。
演劇づくりの裏側と、再生への一歩
演劇の稽古が始まる前段階として、台本執筆という“創作の原点”を描く次回。
脚本が破られるという一見ネガティブな展開は、久部が“こだわり”を手放して、新たな形で人と向き合う転換点になるかもしれません。
第3話は、WS劇場が“劇場”として再生するための、最初の小さな火花になるエピソードといえそうです。
まとめ
『もしがく』第2話では、WS劇場という過去と現在が交錯する空間で、新たな物語が静かに、しかし確実に動き始めました。
主人公・久部三成が打ち出した「ストリップ劇場から小劇場への転換」という大胆なビジョンは、単なる改革ではなく、夢・演劇・人間関係を再構築する挑戦そのものであったように思えます。
『夏の夜の夢』という題材の選定、そして巨大な蚊取り線香という象徴的な舞台装置により、“現実から一歩外れた夢の空間”が演劇として立ち上がろうとしている様子が鮮やかに描かれました。
まだ対立や葛藤は多く、団結にはほど遠い劇場内の人間模様も、第3話以降でどのように変化していくのか注目されます。
次回からは、いよいよ久部の台本づくりと、稽古のスタートが本格化。
この「夢の上演」が、単なる舞台に終わるのか、それとも彼らの人生を変える出来事になるのか──その行方を見届けたくなるような第2話でした。
- 『もしがく』第2話の展開を解説
- クベ版『夏の夜の夢』と舞台劇への転換が始動
- 巨大な蚊取り線香は日本の夏と幻想の象徴
- 久部の野心と情熱が物語の核として浮上
- リカやモネとの対立が描く価値観のぶつかり
- ストリップ劇場から演劇空間への再生の物語






コメント