2025年8月10日放送の『19番目のカルテ』第4話では、糖尿病と診断された患者とその妻のすれ違いを通じて、疾患と病いの違い、そして総合診療医ならではのアプローチが描かれました。
物語の軸となる「森を意識して木を見る」という言葉は、目の前の症状だけでなく、患者の生活背景や心理的要因まで視野に入れる重要性を示しています。
今回は、第4話のあらすじや印象的なシーンを振り返りながら、糖尿病の基礎知識や関連図の意義、そして夫婦関係と治療の関わりについて解説します。
- 『19番目のカルテ』第4話のあらすじと夫婦の葛藤
- 疾患と病いの違いと総合診療の視点
- 関連図やW問診による背景把握の重要性
『19番目のカルテ』第4話あらすじ
2025年8月10日放送の『19番目のカルテ』第4話では、糖尿病と診断された安城耕太と、その妻・早智の複雑な心のすれ違いが描かれました。
単なる病気の治療ではなく、夫婦の関係や心理的背景に踏み込み、「森を意識しながら木を見る」という総合診療科ならではの視点が際立つ回でした。
本作は、疾患の背後にある人間模様を解きほぐすことで、患者と家族が前向きな一歩を踏み出す姿を丁寧に映し出します。
糖尿病が発覚した安城耕太と妻・早智
健康診断で糖尿病が発覚した耕太(浜野謙太)は、半年間にわたり妻・早智(倉科カナ)とともに食事管理と通院を続けてきました。
しかし、努力にもかかわらず数値は改善せず、早智は次第に苛立ちを募らせます。
一方の耕太は、妻の期待に応えられない焦りと、病気そのものへの恐怖を抱えていました。
主治医への不満と総合診療科への依頼
早智は「説明が足りない」と主治医に不満をぶつけ、対応に困った内科医・鹿山(清水尋也)は総合診療科の徳重晃(松本潤)に依頼します。
鹿山は効率重視の診療姿勢を崩さず、表面上は患者に寄り添わないように見えますが、背景の複雑さに戸惑いを隠せません。
ここから、夫婦の本音を引き出すための診療プロセスが始まります。
「森と木」の視点とW問診の提案
徳重は「森を意識しながら木を見る」という理念を掲げ、病名(木)だけでなく、その背景(森)に目を向けます。
夫婦を別々に診るW問診を提案し、鹿山は耕太から、滝野(小芝風花)は早智からそれぞれ話を聞きます。
夫婦のなれそめや日常の出来事から、治療が進まない理由を探っていきます。
弁当をめぐるすれ違いと父の病歴
早智は毎日、栄養管理を考えた弁当を用意していましたが、耕太は昼食を外食後に弁当まで食べていたことが判明します。
その理由は「頑張ってくれている妻を傷つけたくない」という思いからでした。
さらに、耕太の父も糖尿病を患い、家庭に厳しい制限をもたらしていた過去が、彼の心に大きな影を落としていました。
本音の衝突と心の解放
診察中、耕太は「離婚が妻のためになる」と告げ、早智も離婚を考えていたと打ち明けます。
しかし、徳重と滝野は「ここは病気と向き合う場所」と諭し、互いの気持ちを話し合うよう促します。
耕太は父の闘病を見てきた恐怖や、自分の弱さを吐露し、早智も「私の人生にはもう耕太がいる」と応えます。
夫婦の再出発
「嘘をついた、幸せにするって約束できない」と涙する耕太に、早智は「それでも一緒にいたい」と手を差し出します。
二人は手をつなぎ、病気と共に歩む覚悟を新たにしました。
帰り道、耕太は職場の同僚に病気を打ち明け、少しずつ前に進もうとします。
総合診療の価値
理想論だけでは病気は治せないと滝野は悟り、徳重も「小さな積み重ねが大きな変化につながる」と語ります。
第4話は、疾患と病いの両面に向き合う総合診療の本質を示す物語として深い余韻を残しました。
糖尿病とは?
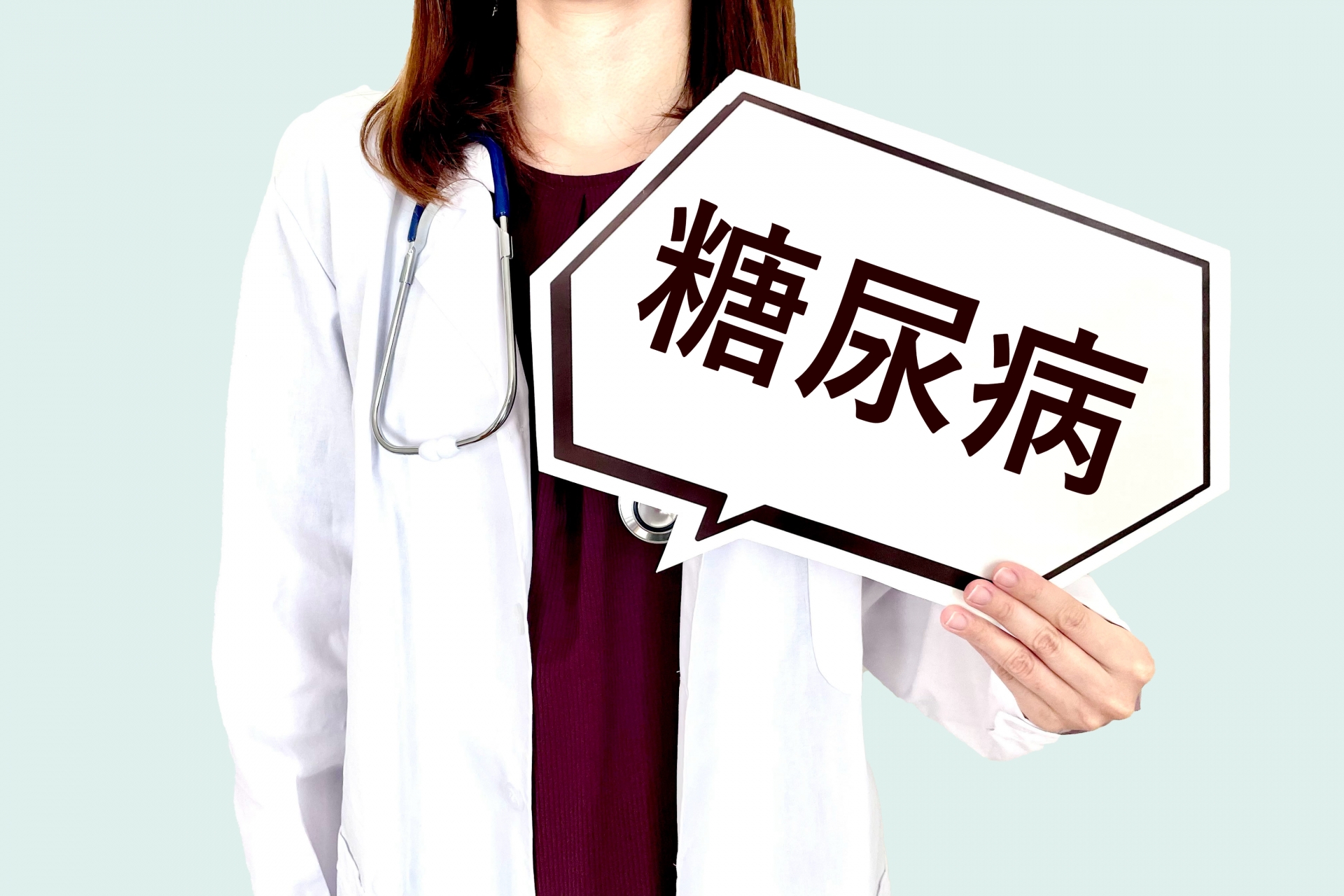
糖尿病はインスリンの分泌不足や作用不全によって、血糖値が慢性的に高くなる病気です。
進行すると心臓病、失明、腎不全、足の切断などの重大な合併症を引き起こす可能性があります。
生活習慣病の一つとして、日本では年々患者数が増加しています。
糖尿病の原因
原因は大きく遺伝的要因と生活習慣要因に分けられます。
遺伝的要因としては、家族に糖尿病患者がいる場合、発症リスクが高まります。
生活習慣要因としては、過食・高カロリー食・甘い物の過剰摂取、運動不足、肥満、ストレスなどが挙げられます。
糖尿病の症状と治療法
初期症状には喉の渇き、頻尿、体重減少、疲労感、視力低下などがあります。
症状が進むと、神経障害や血管障害が起こり、生活の質が著しく低下します。
治療は食事療法と運動療法が基本で、必要に応じて経口血糖降下薬やインスリン注射を行います。
近年は、持効型と超速効型を組み合わせた強化インスリン療法や、新しい経口薬も普及しています。
出典:厚生労働省「みんなで知ろう!からだのこと」2024年11月号、慶應義塾大学病院KOMPAS「糖尿病」、世田谷糖尿病クリニック公式ブログ
疾患と病いの違い
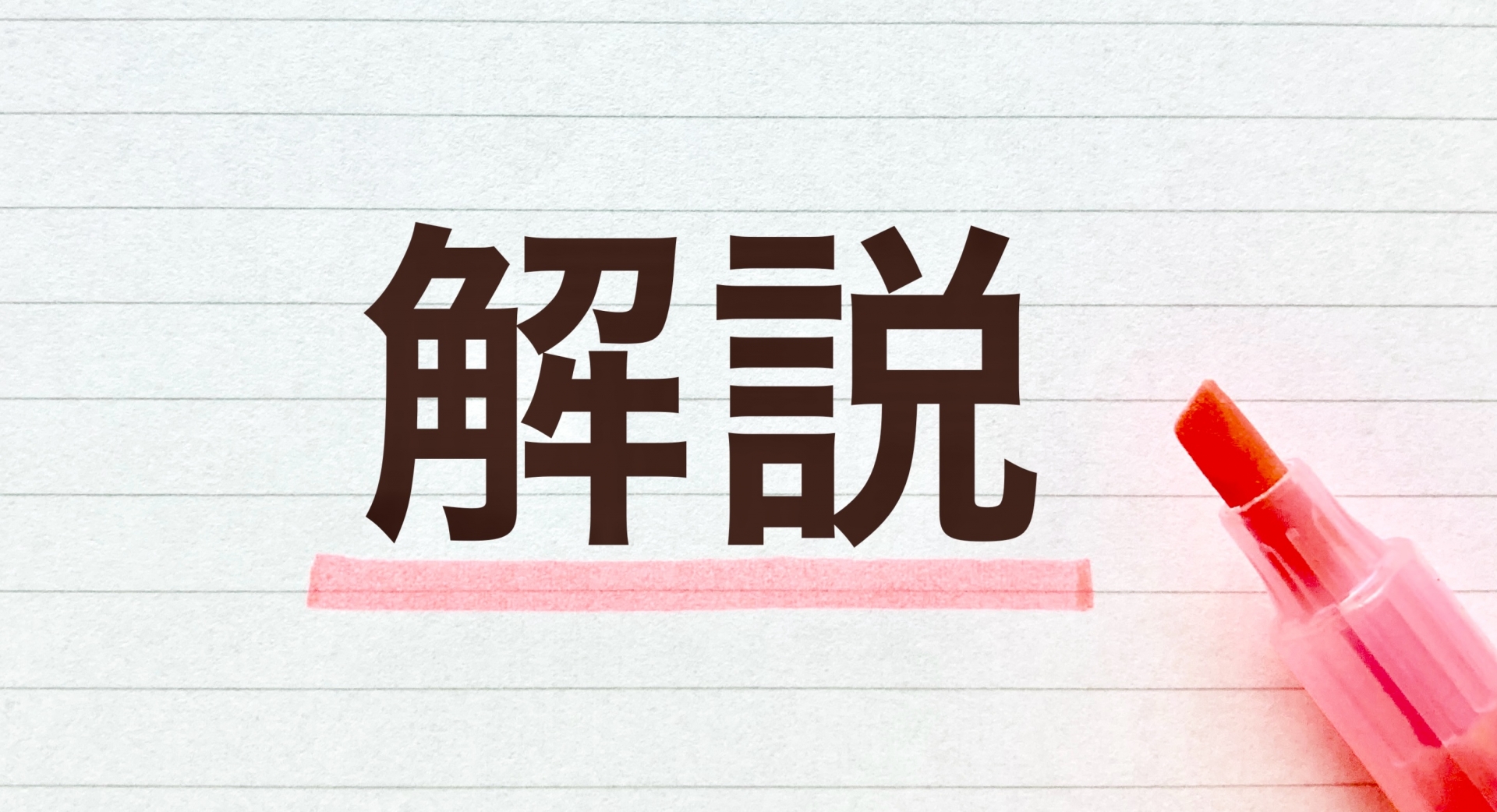
医療現場では「疾患(Disease)」と「病い(Illness)」という言葉が使い分けられます。
両者は似ているようで、実は視点の出発点が大きく異なります。
この違いを理解することは、患者と医療者のコミュニケーションを深める鍵になります。
疾患とは?
「疾患」とは生物医学的に捉えられる身体の構造や機能の異常を指します。
血糖値が基準より高い、レントゲンやMRIに異常所見がある、血液検査で異常値が出るといった、客観的・数値的に示せる状態です。
診断名は疾患を基準に付けられ、治療方針も医学的データに基づきます。
病いとは?
一方、「病い」とは、その人が感じる体の不調や不安、苦しみのことを指します。
同じ病名の患者さんでも、病いの感じ方は人それぞれです。
例えば、
- 糖尿病と診断されたAさんは「特に症状もなく、普段通り生活できる」と感じている。
- 同じく糖尿病と診断されたBさんは「食事制限がつらく、将来の合併症が不安」と感じている。
- 同じく糖尿病と診断されたCさんは、自身の母が糖尿病で透析をしている姿を間近で見ており、将来が不安。
Aさん、Bさん、Cさんは同じ疾患(糖尿病)を持っていますが、病いの経験は異なります。
病いは数値では測れず、心理的・社会的な背景によって大きく左右されます。
疾患と病いから人は苦しむ
患者はしばしば疾患と病いの両方に苦しみます。
医学的治療で疾患をコントロールしても、生活の質(QOL)が改善しない場合があります。
そのため、総合診療では疾患だけでなく、病いの背景を理解し、心理的支援や生活環境の改善を含めたアプローチが求められます。
出典:石川輝「疾患と病いの違い〜患者さんの視点で考える〜」、好書好日「患者は『病い』を経験する」、J-STAGE「病いの当事者性と患者の心」
森を意識しながら木を見る

「森を意識しながら木を見る」とは、症状や検査値といった“木”だけに注目するのではなく、その背後にある生活環境や人間関係、社会的背景といった“森”全体を視野に入れる診療姿勢を指します。
第4話では、徳重医師(松本潤)が鹿山(清水尋也)と滝野(小芝風花)に向けて、「見えないものを一歩引いて可視化する」重要性を説きました。
患者にはすぐに分かることと、分からないことがあり、一見表に強く出ている行動の裏には必ず理由がある――そんな前提に立ち、マクロな視点で患者像を描くことが強調されます。
患者を俯瞰で見る
徳重は「ミクロのレンズになりがちな診療から一歩引き、マクロで見る」ため、患者の背景を図式化します。
そこには病状や検査値だけでなく、夫婦関係、生活習慣、職場環境、家族歴といった情報が整理され、治療が進まない原因を可視化しました。
これにより、単なる糖尿病のコントロール不良ではなく、夫婦間のすれ違いや過去の経験による心理的負担が核心にあることが見えてきます。
実際に看護学生が実習で学ぶ関連図
実際にこの図式化する方法は看護学生が実習でも学ぶ方法です。
関連図とは、患者の情報と情報のつながりを示した図のことです。作成することで病態や状況を視覚的に把握でき、情報整理にも役立ちます。
関連図には大きく分けて、病態関連図と全体関連図の2種類があります。
- 病態関連図:主に疾患の発症メカニズムや症状、検査値、治療との関係を図式化したもの。
- 全体関連図:疾患だけでなく、患者の生活背景、心理状態、家族関係、社会的要因なども含めて全体像を示したもの。
看護学生の臨地実習では、例えば主訴を中心に置き、その周囲に既往歴、生活習慣、心理状態、家族関係などの項目を配置し、矢印や線で因果関係を示します。これにより、ケアの優先順位や看護計画の根拠が明確になります。
広い視野が導く治療方針
徳重先生はこの2つの関連図を作成するやめに夫婦別々に診るW問診を提案し、それぞれの本音や不安を引き出していたのです。
この結果、治療は食事制限や薬物療法だけでなく、夫婦間の信頼回復とストレス軽減を柱とする方向に変化しました。
「森と木」の視点は、数値改善だけを目的としない、患者と家族の生活全体を見据えた治療へとつながります。
医療現場での意義
日常診療では、限られた時間や多忙さから“木”だけを診る傾向が強くなります。
しかし、患者の真の課題は数値や所見だけでは分かりません。
徳重の言葉は、全体像を俯瞰する総合診療医の矜持を示すものであり、医療者にとっても大切な教訓となります。
『19番目のカルテ』第4話の感想

第4話は、糖尿病という慢性疾患と、夫婦関係のすれ違いが絡み合う複雑なテーマを描きながらも、総合診療科の視点で問題を解きほぐしていく過程が印象的でした。
特に「森を意識しながら木を見る」という徳重の言葉は、医療者だけでなく、日常生活の人間関係にも通じる普遍的な視点として心に残ります。
鹿山が面倒事を避けようとする一方で、徳重は一歩引いて全体像を見極め、滝野は感情的になりながらも患者の思いを拾い上げる——3人の医師の対比も見どころでした。
夫婦のリアルな描写
安城夫婦のやり取りは、単なるドラマの演出以上に現実感がありました。
「食事制限を守ってほしい妻」と「プレッシャーを感じながらも言い出せない夫」という構図は、実際の糖尿病患者とその家族にも多く見られる葛藤です。
お互いを思っているのに、伝え方や受け止め方の違いで溝が深まる——このリアルさが視聴者の共感を呼びました。
総合診療の本質を描く
病名や数値の改善だけでなく、生活の質(QOL)と心理的安定を重視する治療が描かれたことは、このドラマの大きな魅力です。
W問診や関連図の活用は、現場での実践例としても有用で、医療者や医療系学生にとって学びの多い内容でした。
一方で、「病気と一緒に生きる」という覚悟を夫婦が共有する結末は、視聴後に温かい余韻を残します。
演技と演出の妙
浜野謙太さんの抑えた演技と、倉科カナさんの苛立ちと愛情が混ざった表情は、キャラクターの感情を丁寧に伝えていました。
また、徳重のセリフの背景に柔らかく差し込む光の演出は、包み込むような優しさを視覚的にも表現しており、SNSでも高い評価を受けています。
第4話は、総合診療の理念を人間ドラマとして昇華させた秀逸な回だったと言えるでしょう。
SNSでの反響まとめ
SNSでは、視聴者から以下のような意見が多く寄せられました。
- 糖尿病と向き合う覚悟に関する声:「糖尿病は完治しない」「生活改善の重要性」「早期発見の大切さ」を強調する投稿が多く見られました。
- 関連図への共感:「看護学生時代に関連図を実習で作成した経験がある」「関連図は大変だが役立つ」という医療系経験者の声が目立ちました。
- 夫婦関係の描写:「はっきり言えない夫にイライラする」「旦那の気持ちも分かる」という両側の立場からの感想が混在しました。
- 日常生活での工夫や課題:「職場での病気周知の必要性」「弁当を残さず食べる行為の意味」など、具体的な生活シーンに言及する意見もありました。
- 行動への提案:「夫は他人の誘いを断る勇気を」「妻は怒り過ぎず冷静に話し合いを」という改善提案も投稿されています。
『19番目のカルテ』第4話まとめ
第4話は、糖尿病という慢性疾患を通して、疾患と病いの両面に向き合う総合診療の力を描き出しました。
「森を意識しながら木を見る」という視点は、検査値や症状だけでなく、患者の生活背景や心理的要因を含めた全体像を把握する大切さを教えてくれます。
安城夫婦のすれ違いと和解の過程は、病気を抱える本人だけでなく、家族全体が治療の当事者であることを示しました。
今回のエピソードから得られるポイントは以下の通りです。
- 糖尿病は完治が難しく、一生付き合う覚悟と生活改善が不可欠。
- 疾患(数値や診断名)と病い(本人の感じ方・心理的負担)は別物であり、両方に目を向ける必要がある。
- 関連図の活用により、症状の背後にある人間関係や生活習慣を可視化できる。
- 夫婦や家族間のコミュニケーションは、治療効果に直結する重要な要素。
医療者にとっては総合診療の本質を再確認できる回であり、視聴者にとっても「病気と共に生きる」という現実と向き合う契機となるエピソードでした。
- 糖尿病患者夫婦のすれ違いと総合診療の視点を描写
- 疾患(Disease)と病い(Illness)の違いを解説
- 「森を意識しながら木を見る」理念の実践例
- W問診と関連図による背景把握の重要性
- 夫婦間の本音を引き出し治療方針に反映
- 糖尿病の基礎知識と原因・治療法を紹介
- 生活背景や心理的要因も治療に影響することを提示
- 病気と共に生きる覚悟と家族の支えの意義を強調







コメント